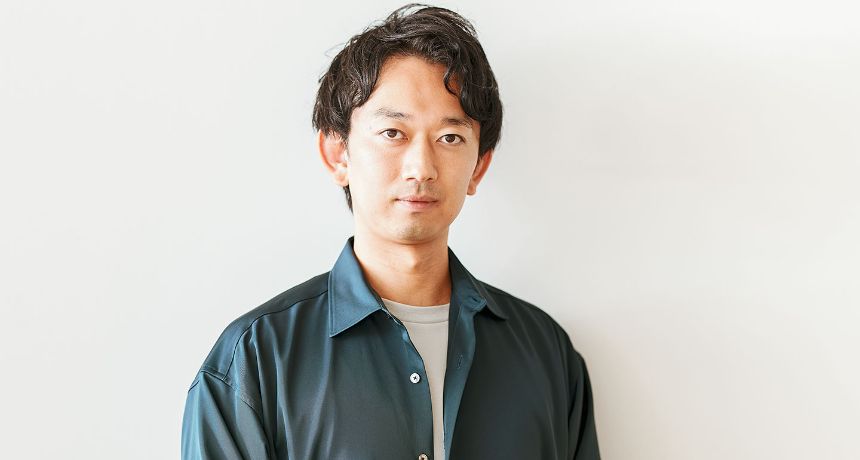誰もが人生の経営者。“本来性への解放”を目指して
2024年11月3日、TYPICAの新社長に葛西龍也が就任した。葛西は1999年に大阪大学を卒業後、上場前のカタログ通販会社・フェリシモに入社し、新規事業創出、事業提携などを担当。コンサルティング子会社やEC子会社、物流子会社の代表などを務めてきた。
「事業活動を通じて社会問題を解決すること」をライフワークとする葛西は、その一環として2008年、PEACE BY PEACE COTTON PROJECT(以下PBP)を立ち上げ、2017年に一般財団法人化。インドのコットン栽培に関連する人権課題や教育課題を解決すべく、インド産オーガニックコットン製品を大手繊維商社やアパレル企業を通じて日本の生活者に販売。売上の一部をプロジェクトの基金として活用することで、現地に有機農法を普及させ、農家の貧困を解消し、子どもたちの教育を支援する循環型事業を実践してきた。
TYPICAと似たアプローチでコットン業界が抱える社会問題の解決に挑んできた葛西が、TYPICAにコミットすると決めたのはなぜだったのか?

気づけばフルコミットしていた
2024年2月に25年働いたフェリシモを退任後、会社を設立した葛西は、人生をリセットしながら新しい事業の構想を練るべく世界一周の旅に出た。旅の途中で寄ったオランダでは後藤将(TYPICA・CEO)と3日間をともに過ごし、公共経営について語り合った。
そんな葛西に後藤が連絡を入れたのは帰国した直後のことだった。TYPICAでボトルネックとなっている物流の問題を解決する人材として、その分野に知見と経験がある葛西が適任だと思えたのだ。
「葛西さんは魅力的で賢い人なので、きっと退職したことを聞きつけた多くの企業からコンサル案件のオファーが来るかと思います。ただ生きていくためだけに仕事を受けて、人生の大切な時間を切り売りしてほしくないし、そんな時間があるならTYPICAを手伝ってほしいです」
そう伝えたものの、葛西からは間髪入れずに断りの返事が返ってきた。
「会社つくったばかりなのに勘弁してよ! 25年間もサラリーマンをやってきてようやく独立したのに、またサラリーマンやるのは嫌だ!」
「わかりました。では業務委託だとどうですか? まずは、TYPICAのビジョンを実現するための物流ニューモデルについてマスタープランをつくりましょう。その計画の実現に自らが本気で取り組みたくなったらTYPICAにフルコミットすればいいし、そうでなければチームづくりまで携わってから契約解除で大丈夫です」

その条件ならば、とTYPICAに関わるようになった葛西は当初、物流の基盤を整備し、その発展形を構築するため、外部の物流コンサルタントにアドバイスをもらいながら仕事を進めていた。
国際物流の大きな流れから見て、対処すべき改善点や導入すべき仕組みは明確だったが、流通取引総額4000億円を実現させる未来を見据えれば、今見えている課題の解決が答えではない。TYPICAの本質的な役割は、84ヵ国・地域に点在する生産者とロースターの媒介役である。生産者からロースターのもとに、予約した生豆が届くバトンリレーのプロセスを社内のメンバーと改めて共有しながら改善を進めることが、今後のTYPICAにとってより重要だと考えるようになっていった。
葛西はいつからか業務委託としてやれる仕事の範疇を大きく上回り、大半の時間をTYPICAメンバーとの対話に使っていた。充実感を覚える胸の内では、道半ばで理想の実現に頓挫した無念がよみがえっていた。

経営=世界の構造を変える手段
葛西は岐阜県出身。将来父が立ち上げる工場を経営するために大阪大学に進学したものの、ほどなくパチンコやバンド活動によりどころを求めるようになった。
将来に希望を見出せない葛西に追い討ちをかけたのが、「父が仕事中の怪我で重傷を負った」という報せだった。父の描いた青写真がひび割れるとともに人生の目的を見失った葛西は、ろくに就職活動もせず、今さえ楽しければいいという半ば自暴自棄な気持ちで日々を送っていた。
転機はふいに訪れた。バーでアルバイトをしていた葛西はある日、自身の率直な気持ちを常連の男性客に打ち明けた。すると「せっかくいい大学に入ったのに、それじゃあもったいないぞ。ちょうどうちで新卒を募集してるから、受けるだけでも受けてみろ」と勧められた。
長髪でクロムハーツの指輪をしている彼は、22時頃に来店し、遅くまでにこやかに酒を飲んで帰るのが通例だった。仕事について詳しく聞く機会はなかったが、どうやらデザイン関係の仕事で海外出張などにも行っているらしい。こういう人が活き活きと働いている会社ならきっと、表面的な部分で人を判断しないだろうし、楽しく働けそうだ──。がぜん興味が湧いた葛西は、どういう事業をやっているのかを知らぬままその会社の選考を受けた。
選考が進み、無事内定を得たその会社がフェリシモだった。「しあわせ社会学の確立と実践」を理念に掲げる同社は、事業性、独創性、社会性の3つが重なり合うところを事業領域として定め、単なるビジネスに留まっていない点で、他のカタログ通販会社とは毛色が異なっていた。内定後、会長の矢﨑勝彦(フェリシモ二代目社長/京都フォーラム理事長)から聖徳太子の『十七条憲法』を手渡され、こう言われたときは衝撃を受けた。
「会社というのは利益を出しながら幸福な社会を作っていく、公の器なんや。そして君たちはその主人公なんや。サラリーマン人生から経営者人生へ。30歳までは会社で面倒を見るけれど、30歳になったら君らも会社をつくるんや」
経営は目的ではなく世界の構造を変える手段である──。矢﨑勝彦からそう叩き込まれた葛西は以来25年、矢崎和彦(フェリシモ三代目社長)の指揮のもと、事業活動と社会課題の解決、生活者の役割認識の発達と事業への参画、業態を超えるパートナーシップによる新規事業の開発に邁進してきた。

その一例がPBPである。9.11同時多発テロの際に企画したチャリティーTシャツは累計20万枚を販売。その後Tシャツの原料となるコットン生産にまつわるインドの農家の問題を知ったときは、循環型で解決する構造をプロジェクト化し、一般財団法人を設立した。
その後新規事業開発の執行役員として、地域経済を活性化すべく大手鉄道会社と提携して進めた越境EC事業、大手メッセンジャーアプリと提携したCtoC定額配送事業、大手農業法人と提携した地域農産物の販売事業、大手物流会社と提携したラストワンマイル配送JVなど幾多のプロジェクトを立ち上げ、実践を重ねた。2020年からはファッション通販ブランドおよびECサイト「haco!」を運営する子会社に集中、翌年転籍し、経営者人生を歩み始めた。
「社会の不均衡を改善し、世界をあるべき姿に持っていくために、生活者を巻き込んだ経営によって産業構造を変え、グローバルで事業を展開していく。そんな構想を描いていたものの、同時に訪れたコロナ禍・急激に進んだ為替変動で受けた打撃から回復しきれず、2024年3月、子会社は清算となりました。僕の力不足によりまだ“アパレル・ファッションのEC会社”というフェーズで頓挫してしまった。それもあるからこそ、同じ師(矢﨑勝彦)のもとで学び、同じ理想を追求し実践している後藤さんは、絶対に失敗させてはいけないんです」

人が大大大大大活躍する事を応援し続ける組織
コットンや大豆、小麦と同じく、コモディティに含まれるコーヒーは、先物取引による国際価格の乱高下、奴隷制度や植民地制度の名残といった共通の構造問題を抱えている。世界の農業界でも、生産物の流通効率を優先するがゆえに、各生産者の個性は顧みられず、画一化された商品として市場に送り出されている。
「ダイレクトトレードで生産者とロースターを媒介するTYPICAがシンボリックな存在になって世界の標準を変えることができれば、他の分野にも波及してコモディティ市場の構造や農業全体の改革にもつながると思います。コーヒーは品質や価格と味(体感)が連動していることがわかりやすいので、コットンや大豆と比べてもより実現可能性が高いのかなと。
人間って、生まれたときは無限の可能性に満ち溢れているのに、大人になるにつれて少しずつ見切りをつけていくじゃないですか。だから僕にとっては、自分で販売価格を決められず、成長、拡大できる機会が制限されているコーヒー生産者、綿花生産者も、決まった給料のなかで生活をやりくりして、夜になると酒場で会社の文句を言っている日本のサラリーマンも根は同じ。ルールや仕組みの中に人間が閉じ込められるのではなく、それを超えて人間の可能性が発揮する社会は実現できるし、実現しなきゃいけないと思っています。
究極の理想は、あらゆる人が何にもとらわれず、あるがままに生きられる世界だけど、現実的に、才能や能力の問題でそれが叶わない場合もある。でも、可能性を実現させようと挑戦を続けるのと、あきらめて惰性で生きるようになるのでは、圧倒的に前者の方が豊かな人生だと思うんですよね。人が大大大大大活躍することを応援し続ける組織の在り方を追求するのも、TYPICAにとってとても重要なテーマだと思います。
TYPICAで掲げる流通取引総額4000億円という目標は、決まりきった枠組みやチーム、予算編成の積み上げでは絶対に達成できない。中心に人を置き、関わる人の可能性が無限に広がり続けることでようやく見えてくるものだと思います。
会社組織を永続的に成長、発展させていくためには、ある程度ルールを設け、体制を整備していくことは必要なプロセスです。ただ、ルールは一度出来てしまうと守ることが目的になり、それ以上の発展を阻害する要因にもなる。ルールは守るものではなく、より開かれた未来に向けて柔軟にバージョンアップし続けていくものだという認識を皆が持って共働し続けられるような組織づくりを進めていきたいと思っています」

そう語る葛西の人生のテーマは「奴隷性からの解放」だ。制度としての奴隷「制」ではなく、人に決められた事だけをする「性質」や、依存して人のせいにする「性質」に葛西は目を向けている。問題意識の核にあるのが、易きに流れ、都合のいい言い訳で自分を正当化しながら、自らの可能性、主体性、能動性に蓋をする人間の奴隷「性」なのだ。
「亡くなった会長と最後に約束したのが、このことなんです。どこまでも能動的に、内発的に、人が発展し続けるからこそ、いろいろな困難は解決していける。人間の本来性への解放というテーマが実現できたとき、さまざまなものを分断し、差別し、区別してきた社会構造から本当の意味で次に行けるのだと。
正直、会社が清算された時は『もう47歳。一つの山を登りきったのかな』という感覚もありました。25年間の社会人人生で、新規事業の開発からIPO、執行役員、経営まで経験させてもらったからです。ただ、何か諦めきれなかったし、いまでも諦めていないのかもしれません。仲間とまだまだ航海を続けたかった。世界一周して様々な国に行き、多様な価値観、宗教観、生活観に触れて感じたのは、やはり自分は小さな世界に囚われていたな、ということでした。
流通させるコーヒー生豆の質、量ともに世界一を目指すTYPICAと関わるようになって自覚したのは、自分が登ってきた山は高くそびえ立つ山々が連なる山脈の一部にすぎなかったということ。だから、今までの経験をコーヒー業界に還元していこう、などという驕った気持ちはさらさらありません。あくまでもひとりの挑戦者・経営者として事業、産業、そして世界の永続的発展(サスティナブル・デベロップメント)に貢献したいんです。そのために常に最適を追い求めながら、目標の実現可能性を高め続けていきたいと思っています」