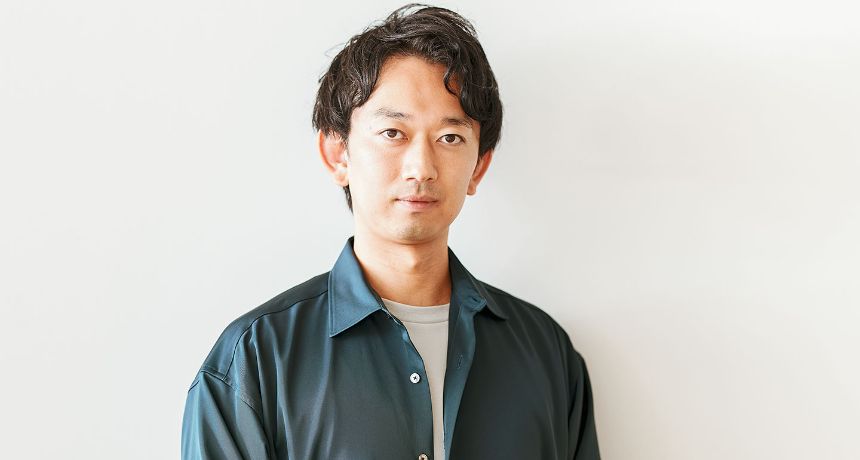“真面目な”人が報われるように。システムの力で民主化された世界を
2024年9月、TYPICAのニューモデルを構築するプロダクトチームに新しいエンジニアが加わった。現在、執行役員を務める有澤高介の紹介で入社した荒井栞だ。二人は前職のラクスル時代、同じチームで3年ほど働いた縁があり、プライベートではゲーム友達でもある。
筑波大学の情報系学部を卒業後、「Webシステムで世界を変えたい」という思いを軸にWebエンジニアとして働くこと10数年。自身初となるスタートアップでの挑戦を決めた荒井の胸にある思いとは。

「幸せ」に対する認識が揺らいだ
「あなたは今幸せですか?」
採用面談中、コーヒー生産者が抱える貧困問題等について語るTYPICA・CEOの後藤からふと投げかけられた問いを、荒井はずっと忘れることができなかった。30代半ばに差しかかり、この先の人生をどう生きていくのか、改めて考えるタイミングでもあったからだろう。他の転職候補先を探しているときも、その言葉は常に頭の片隅に居座っていた。
「もちろん、世界には貧困や飢餓に苦しんでいる人がたくさんいることも、経済格差を解消するためにフェアトレードがおこなわれていることも知識としては知っていました。でも、これまでずっと日本で生きてきたし、それを強く実感したことはない。だからハッとしたんですよね。日本だけをよくしても世界はよくならないんじゃないか、というのは一理あるなと。
現に、TYPICAはグローバルにビジネスを展開していて、いろんな社会問題も解決できる。みんながそう信じてやっているところに惹かれたんです」
Webシステムによって世界をいい方向に向かわせたい。新卒の頃からそう思って仕事をしてきた荒井にとって、5年半勤めた前職のラクスルはもっとも濃い時間を過ごした場所だった。
「仕組みを変えれば世界はもっとよくなる」というビジョンを掲げるラクスルは、印刷や集客支援のシェアリングプラットフォームである。資本や人材といったリソースを持たない中小企業や個人事業主が、安価かつ手軽に高品質な印刷物をつくり、事業を成長、発展させる機会を提供している。
「ダイレクトトレードを促進させるTYPICAのビジネスモデルは、ラクスルに近いところがあります。家族でやっているような小規模農園でも自分たちの名前でコーヒーを流通させて、ファンをつくることができる。生産者とロースターの顔の見える関係を媒介すればするほどTYPICAも潤う。そのあり方に共感したんです」

コンフォートゾーンを抜け出して
一方、ラクスルとTYPICAでは成長ステージが大きく異なる。すでに基盤が整っており、拡大期に差し掛かっていたラクスルに対して、これから基盤を整えていく段階のTYPICA。有澤からも「カオスだよ。チーム開発の経験が少ない人が多いから、いくらでもやることあるよ」と言われたが、荒井はそれを前向きに受け止めていた。
「ラクスルが10から100、100から1000にするフェーズだとすれば、TYPICAは1から10にあたるのかなと。新しいプラットフォーム(ニューモデル)が動き出したばかりで未完成なところが多いからこそ、自分の経験やスキルを共有するなり、他部署と連携して業務を効率化するシステムを導入するなり、自分が貢献できる部分がたくさんありそうでワクワクしています。
私自身がIT技術に関して“非ネイティヴ”だったからこそ、専門知識を持たない一般的な会社員の人たちでも活用していけるような橋渡しをしていきたいんですよね。これまで属性が近しく、共通言語で会話できる人たちと働くことが多かった私には新たな挑戦。もっと広い世界で自分のスキルや経験を活かしたい、と思ったんですよね。
実際、TYPICAはコーヒー業界では先進的なベンチャーとして知られているものの、IT業界では知らない人も多い。IT業界の人たちも注目するようなおもしろいプラットフォームやサービスをつくることで、会社の成長や株式上場に貢献したいと思っています」
かくいう荒井だが、過去にもスタートアップに関わるチャンスがあった。ラクスルへの転職を決める前、大学時代の先輩から「スタートアップを一緒に立ち上げないか?」と誘われたのだ。魅力的な勧誘に心は動いたが、自分の現在地を思えば冷静にならざるを得なかった。まだ経験が浅いのだから大した戦力にはなれないだろう。そんな心の声が、リスクある挑戦から荒井を遠ざけていた。
「すでにある程度形になっているものをフォーマット化して、皆が使えるように広めていくのが自分の得意分野。そう認識していたので、ビジネスモデルも仕事のやり方も確立されているラクスルなら拡大期に貢献できるかなと思ったんです。
逆に言うと、TYPICAのようなフェーズで自分が役に立てるイメージはあまり湧かなくて。だから、自分が成長できる環境や引き出しを増やせる仕事を探していたのですが、TYPICAのビジョンに深く共感したことで考えが変わった。自分に適性があるかどうかわからない、組織が整っていないという理由で、自分が本当にやりたいことをやれるチャンスを逃しちゃうのはもったいないと思ったんですよね」

いかにITでインパクトを出せるか
「ネットサーフィンと読書を好むオタクだった」荒井が、WindowsXPでインターネットに触れ始めたのは小学4、5年頃のことだ。わからない単語があったとき、その単語を検索すればまたわからない単語に出会えるのだ。無限に新しい世界が開けていくようなインターネットの海を回遊する時間は、我を忘れて没頭できた。
中学生になると、インターネットを通じた人とのつながりが生まれた。テキストチャットで知り合った女子高生や女子大生と一緒にゲームセンターに行って遊んでいると、少し大人になれた気がして誇らしかった。「中学生の女子」というラベルで見られず、対等な人間として付き合えるのが新鮮でもあった。
「学校で嫌な思いをしていたわけでもなく、リアルな自分に不満があったわけでもないけれど、ネットの世界とリアルな世界は完全に切り分けて考えていた気がしますね。仕事を始めてインターネットの向こうには必ず人がいると実感するようになってからは、自分の中でネットとリアルの垣根はなくなってきたと思います」
荒井が10代を過ごした2000年代は、ITが急速に人々の生活に浸透していった時代である。mixiやTwitterなどのSNSを通じれば、言語や場所を問わず人とつながることができ、画期的なWebサービスを活用すれば、圧倒的にタスクが効率化できる。ITによって世界がもっといい方向へと向かう可能性を感じた荒井は、ITエンジニアに必要な技術や知識を学ぶべく、筑波大学の情報系学部に進学した。
だが、そこには壁が待ち受けていた。独学でプログラミングのスキルを身につけた学生や、ベンチャー企業でアルバイトをしながら実践技術を磨いている学生を前に、荒井は負い目を感じずにはいられなかった。言うなれば、趣味で英語を学んできた人間が、ネイティヴスピーカーの集団に混ざったようなものである。この世界で自分はやっていけるのだろうか、そんな不安に苛まれた4年間が、堅実に経験やスキルを積み上げていく道を荒井に選ばせた。

大学卒業後は、請負開発を主とするSIer(A社)に入社し、Webアプリの開発に携わった。Webシステムを導入することで、ハンコリレーのような伝統的な日本企業特有の無駄が解消され、一気に効率化する場面に幾度も立ち会い、DXの可能性を体感した。
A社で自社サービスの開発に興味が湧いた荒井は、ホテル向けSaaSを開発する会社(B社)に転職して働くこと約2年、フロントからバックエンド、インフラまで全体をカバーする仕事を経験した荒井は、より専門性の高いメンバーとより大きな規模感で開発に携われる会社を求めてラクスルに転職。toB領域はITで効率化できる余地が大きく、仕事の自動化によって社会や個人に与えるインパクトも大きいと感じていたからだ。
そこで出会ったのが有澤だった。有澤は当時、複数のECサイトで汎用できるデータチェックの基盤システムをつくるプロジェクトをひとりで進めていた。荒井もメンバーの一員となったそのプロジェクトチームは、印刷物の受発注から納品までの作業工程の一部を自動化。顧客や売上の増加とともに、生産性、収益性の向上に大きく貢献した。
「その基盤システムの開発は、エンジニアとして一番大きな成功体験です。ラクスルは印刷プレビューが見れたり、納品までの日数を正確に把握できたりとUXもよく、同社のサービスを使う意味を提供できていたかなと思います」
有澤は言う。「荒井さんとはツーカーで話せる仲だし、toBのビジネスに慣れている。マネジメント経験もあれば、ベンチャー企業(B社)で鍛えられた経験もある。おまけに人柄も明るくて親しみやすい。だから、新作のゲームが出たタイミングでたまたま連絡したときに『ラクスルをやめる』と聞いたので、すぐに誘いました。TYPICAでは細かいところにまで目を行き届かせて、積極的にルールメイクや業務の効率化を進めてくれているので助かっています」

共存共栄のビジネスモデル
インターネットには、善も悪も人の手に負えない規模にまで増幅させる側面がある。テクノロジーそのものに罪はなく、つくる側、使う側の倫理観に委ねられるが、秩序なき世界では悪は蔓延してしまうため法規制が導入される。その結果、真面目にやっている人間が不利益を被るーーという状況はあらゆる時代や分野で発生する。
それゆえに荒井は、ユーザーの射幸心を煽って利益を得る事業分野や、ゼロサムゲームでお互いに利益を奪い合う業界など、貴重な労力を費やしてやる意味があるのかと疑問を感じるサービスには、仕事では関わらないようにしてきた。
視点を変えればそれは、インターネットによってさまざまな分野で民主化が進んだ証である。ビジネスにおいては、資金や知名度のない中小企業や個人にも機会が開かれ、チャンスを掴み取れる可能性が一段と高まった。
「たとえリソースが限られていたとしても、自分に合ったサイズ感でビジネスをやって幸せに生きていける世の中の方がいいと思っています。プラットフォーマーは時に“手数料を搾取して利益を得ている悪者”と見られますが、少なくともラクスルは共存共栄でした。
TYPICAも同じだと思いますが、お金を効率よく稼ぎたければ、他にもっといいビジネスモデルがあるはず。肩書や属性に縛られず、権力やお金を持っているかどうかにも左右されず、誰もが機会にアクセスできるような民主化された世界をつくっていきたい、という思いが私の根っこにはあるんです」

真面目な人間が損をしていいのか?
そう語る荒井の源流には、母親から繰り返し言われてきた「あんたと私みたいな真面目な人間は周りにいいように使われて損するんだよ」という言葉がある。
パートで働く主婦だった母は、仕事ができる人だったらしい。だが職場で気を回して、問題を未然に防いだり、課題を解決したりしても、誰も評価してくれず、給料も上がらない。かといって、気づいている自分がやらなければ誰かが困ると思えば、見て見ぬふりをすることができない……。母の葛藤はよく、愚痴へと形を変えていた。
その背後には、大手保険会社の総合職として働いていたものの、結婚、出産を機にやむなく退職し、家庭に入った過去がある。子どもが巣立った今は派遣社員として働いているが、パートの事務職としての経験や実績は評価の対象にならない。元来、仕事が好きで能力も高いのに、それを活かせない悔しさやもどかしさはずっと胸中にあったのだろう。
娘には同じ思いをさせたくないという気持ちが強かったのか、高校時代、荒井がグループワークの課題を毎晩、夜遅くまでやっていると、母は「それはほんとにあんたがやらなきゃいけないことなの?」としきりに声をかけてきた。小学校時代、クラス内に漂う重苦しい空気に耐えかねて、やりたくもない学級委員長を引き受けたことを思えば、荒井自身に心当たりもある。
「真面目な人間は損をすると言われたからといって、やる必要がないとは思わなかったし思えなかった。短期的に見れば損をしているかもしれないけれど、いずれ自分のためになると思えば納得できたんです。仕事でも、自分が見つけた課題を変えていこうとチームメンバーに提案したとして、共感されない場合は自分でやるしかない。たとえそれが、背負わなくてもいい苦労だったとしてもです。
だからこそ、真面目な人間が損をするような社会は嫌だ、正しいことをしている人が報われる世界であってほしいという願望が私の中に生まれたんだと思います。簡単には儲からない分野や難しい事柄に挑戦している人たちの力になって成果をあげることで、過去の自分や母のような人たちも含めて報われるように感じているのかもしれません」