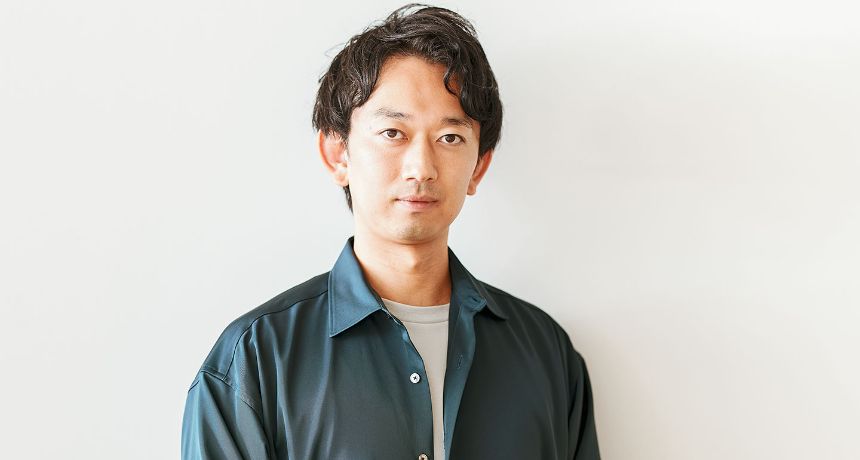初期衝動をもう一度。創りたい世界へ一心に向かう
大学卒業後、コーヒーのプロになりたい、いずれは自分でカフェをやりたいという思いを胸に生豆を扱う輸入商社石光商事に就職。生豆の品質管理やカッピングから中国・上海での子会社立ち上げ、生豆の買付や営業、さらには焙煎したコーヒー豆のフードサービス市場向けマーケティングまで、さまざまなポジションからコーヒーのサプライチェーンに携わること15年。2023年4月、TYPICAに入社した松下翔太は今、コーヒーエキスパートチームの一員として、中規模、大規模ロースターの新規開拓、関係構築を担当している。
「2030年までに流通額4000億円、アラビカ種の33%をTYPICAで流通させる」という壮大なビジョンに触発されて入社した松下が約2年経った今、思うこととは?

純粋な自分がよみがえってきた
麻袋一袋(60kg)からのダイレクトトレードにより、コーヒー業界に変革をもたらしてきたTYPICAは、2019年の創業以来、従業員数名〜数十名程度のマイクロロースターに顧客ターゲットを絞り、事業を展開してきた。2023年からは、中〜大規模ロースターにターゲットを拡大。コーヒーエキスパートチームの松下は、その推進役を担っている
「普段の顧客とのコミュニケーションでは、コーヒー豆の品質や価格面でのメリットを訴求するのではなく、同じ船に乗る同志をつくる感覚で一緒に創りたい未来や世界について語っています。たとえば『コーヒーの2050年問題を解決するためには、小規模生産者がコーヒーを作り続けていただくことが不可欠です。人々から愛され、楽しまれる飲み物の未来を一緒に創っていきましょう』というように」
当初は、すでに決まった調達ルートを持っている中〜大規模ロースターには検討すらしてもらえないことも多く、障壁の高さを感じていた松下だが、ここ数ヶ月で潮目が変わってきたことを実感している。
「サステナビリティに関する取り組みが遅れている、あるいはブランドの競争力が落ちてきているという問題意識を抱えた企業さんとの成約が決まるなど、関係が前進しているとき、新しい時代をつくっている感覚を得られます。提案の前段も含めて、実現していきたい未来、実現しうる未来を想像するとワクワクするんです」
同じコーヒー業界でも、組織体制が確立され、ルールが明確化された会社で15年間働いてきた松下にとって、スタートアップへの転職には心の準備が必要だった。何もかもが違うだろうから、今までの常識は捨て去らなければならない。そう覚悟してTYPICAで働き始めた松下は、素直に学ぶ姿勢を維持してきた。今となってはむしろ、自分よりも後に入社したスタッフの意見を聞いてハッとさせられることもある。
「入社当時驚いたのは、仕事に対するメンバーの意欲や姿勢が気持ちいほどピュアだったこと。皆が同じ方向を向いてるし、ポジティブで後ろ向きなことは言わない。会社のビジョンもミッションも明確で、それに賛同した人たちが集まっている。
たとえばコミュニティマネージャー間での毎日のミーティングでも、何をどこにどうやって売るかではなく、どういう世界をつくっていきたいかという本質を見失わないようにする姿勢は一貫していた。そんな世界に身を置いていると、コーヒーの仕事をしたいと思った20歳の頃の純粋な気持ちがそっくりそのまま蘇ってきた感覚があったんです」

ただただコーヒーが好きだった
コーヒーが松下の人生の一部を占めるようになったのは高校生の頃だ。といっても、スターバックスなどのお洒落なカフェで友達と話をしたり、デートをしたり、テスト勉強をしたりする時間や空間こそが目的であり、コーヒーは端役にすぎなかった。
だが何度もカフェに通ううちに、松下はコーヒーの味が違うことを知覚していく。時は2000年代前半。折しも「スペシャルティ」という言葉が一部では聞かれるようになり、先進的なロースターやカフェが出所のわかるコーヒーを提供し始めていた時代である。同じ国のコーヒーでも農園によって味が違うのはなぜか? どうすれば美味しく淹れられるのか? 日々、“研究”に励む中で、コーヒーは趣味の領域に留まらなくなっていた。
やがて松下は「焙煎や抽出も大事だが、どこでどう作られたかの方がコーヒーの味を大きく左右するのではないか」という仮説にたどり着く。ダイレクトトレードのパイオニア的存在である堀口珈琲の店主が産地について語る様子に憧れを抱きながら、松下はコーヒーのプロになりたい、いずれは自分でカフェをやりたいという志を育んでいった。
就職活動中、「その土台づくりとして、まずは美味しさの鍵を握るコーヒー農園に行きたい」という思いに突き動かされていた松下は、直営農園を持っているロースターや商社など、農園に行けそうな会社に絞って採用試験を受けた。最終的に、希望する会社での職を得た松下の心は浮き立っていた。
「入社後は好奇心の赴くままに、先輩に質問しまくっていましたね。だから入社2年目に初めて農園に行ったときは感慨深いものがありました。焼け付くような日差しの暑さも土と木の匂いも、すべてがときめきを与えてくれるものでした。以来、農園には何度も足を運びましたが、農園に身を置くたび、僕たちは自然の恵みをいただいているんだと思い出すことができた。日本で仕事をしていると、コーヒーが工業製品のように思えるときもありましたからね」
だが社会で揉まれるうち、自分でカフェをやりたいという目標はいつしか胸の内から消え去っていた。顧客として付き合っているロースターやカフェが価格競争に走ることも多く、営業としてそのニーズに日々対応していたからだろう。好きという気持ちだけで続けていくのは厳しいと、ひとつの可能性に見切りをつけたのである。
「20代後半で結婚し、子どもが2人できたことも安定志向、現実思考になった一因です。その意味ではTYPICAに転職することに迷いはなかったけれど、チャレンジングな決断ではありましたね」

ゲームチェンジが起こったならば…
松下の心がTYPICAに傾き始めたのは、2022年秋頃のことだ。日本最大規模のコーヒーの展示会(SCAJ)に出展しているTYPICAのブースを見たことがきっかけである。
スタートアップらしく勢いがありながらも、粗っぽさがなく佇まいも整っている。そんなTYPICAが心の一角を占めるようになって以来、ホームページに時折アクセスし、「コーヒーそのものではなく人にフォーカスしている」スタンスにも惹かれていった。
偶然にも松下自身、当時は日本の焙煎工場でつくったコーヒー豆を海外展開するために動き始めた時期だった。人口減少により日本市場が縮小していく中で、グローバルに足場を広げていかなければ先細りしてしまう。そんな危機感とは裏腹に、社内では思いを分かち合える仲間は少なく、片手間でやっている感覚が拭えなかった。
会社の労働環境こそ申し分なかったが、自分の評価や待遇が貢献度と見合っていないという不満も、松下の目を外に向けさせた。新天地を求めて転職活動を進めていた中で自身のニーズと重なったのが、グローバルビジネスを前提にしているTYPICAだった。

「心が大きく動いたのは、Web面接でTYPICAのビジョンを聞いたタイミングです。『2030年までにアラビカ種の33%を流通させる』というスケール感に驚くと同時に、そういう世界が現実になったときの未来を想像すると、自分も当事者として関わりたくなったんです」
そもそもコーヒー豆が扱われる先物取引市場には、利益のみを目的としたヘッジファンドの投機マネーが大量に流入しており、相場が乱高下しやすいという構造問題がある。その渦中にいる松下自身、予測不可能な値動きに翻弄され、苦しめられたことも少なくない。なかでも2021年、2022年は高騰が激しい厄年だった。
「コーヒーの本質とはかけ離れたところで決まる相場のせいで、値上げのお願いをするためにお客さまに頭を下げて回るのが辛かったんですよね。おまけにボーナスが減って、自分の生活も直撃する。だからといって、自分たちでどうにかできるようなものではないので、相場を日々チェックして予測を立てたりと、少しでもそのダメージを減らすことに心を砕いていました。
ただ、そもそも価格が決まる仕組み自体を変えるという発想はまったくなかった。もしTYPICAのビジョンが実現し、それだけのインパクトを与えられる規模になればゲームチェンジが起こり、コーヒーに携わっている人どうしで値段を決められる世界に変わるんじゃないか、という期待が膨らんできたんです」

心から望む生き方を
ビジネスの世界は基本的に、本音と建前で動いている。どれだけ純粋な志を持って入社したとしても、理想だけでは社会は回っていかないと知り、胸の奥に本音を押し隠しながら働くうちに、賢く生きる術を身につけていくものだ。松下も社会人になって15年、多かれ少なかれそういう場面に出くわしてきたが、“物分かりのいい大人”としてやり過ごすことはできなかった。
「営業としてそれなりに成約が取れていたのは、わりとピュアな気持ちで仕事をしていたからだと思います。もちろん仕事なので、自分が心から売りたいと思っていないものを売らないといけないことも多々あったけれど、値段で釣ったり、トークで気を引こうとしたりするのではなく、商品の本質で勝負できるような営業は常々心がけていました」
松下が前職で終盤に担当した案件は、まさに10数年のキャリアの集大成と呼べるものだった。自分で開拓した大手外食チェーンに対して、その店オリジナルのコーヒーをつくる際、自分が心から薦めたいものを提案した結果、大型の契約を獲得できたのだ。
「前職ではコーヒーの味や品質などのスペックにフォーカスしていたのに対して、TYPICAでは生産者に光を当てています。やっぱり『値段が上がったからもう買わない』となるのではなく、『状況が厳しいときでも買い支えよう』と思える関係の方がいいし、世界は変わりそうな気がするんですよね。もちろんうまくいかないことも多々あるけれど、心が折れそうになったことがないのは、目指している世界があるからだと思います。
僕も今年で40歳。以前はわからないことだらけで気持ちばかり先走っていたけれど、知識や経験、ノウハウがある今は、然るべきところにリソースを割いたうえで効率よく動くことができる。前職で15年間、相場に苦しめられたからこそ、実需に応じた適正価格に取り戻すことで、自分たちやロースター、生産者、生活者、皆にとって幸せな形を実現したいと思っています」

一方で、個々の役割が明確化した中堅企業からスタートアップに転職した松下は、新たな壁にぶつかっている。「一人ひとりが経営者」という組織のあり方を目指すTYPICAで求められるものは、前職とは異なっているからだ。
「前職では、顧客の新規開拓を2年かけて行う、新しく立ち上げた中国の拠点を3年で黒字に持っていくといったミッションに対して、担当者としてプロジェクトを成功させることにフォーカスしていました。一方TYPICAでは、より遠いビジョンから俯瞰逆算し、より広い視座を持って今やるべきことを遂行していく必要があります。
別の言い方をすれば、経営に対してもっとこうすればいいのに…と思うだけで終わらず、行動に移して組織を変えていく機会が与えられている。普段の仕事では、目の前のKPIを達成することに意識が向かいすぎるあまり、自分の『役割』や『担当』とそれ以外の仕事を無意識により分けてしまうこともあるけれど、改めて自分は単なる一プレイヤーではないという自覚を持って主体的に取り組んでいきたいと思っています」