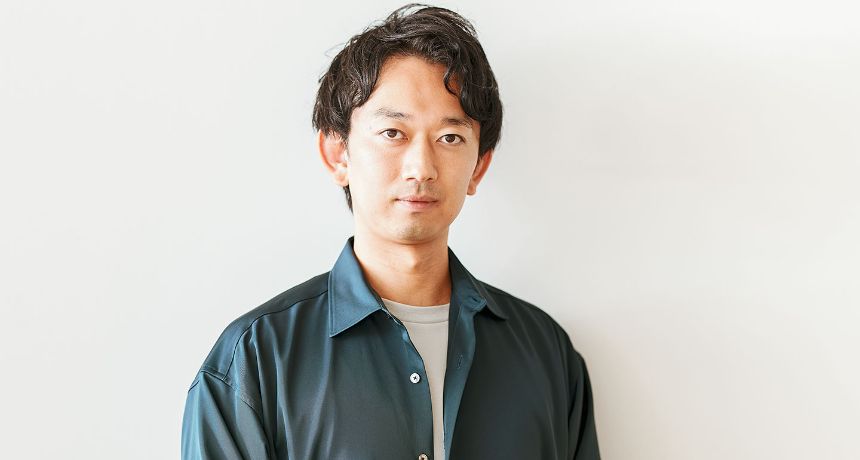「いつの間にか、ここにいた」重ねてきた“今”がひらいた未来
2022年1月に入社以来、韓国担当のコミュニティマネージャーとしてロースターとの関係構築に携わっているシン・ソイ。2019年4月、大学の交換留学で韓国から来日し、大学の授業とロフトでのアルバイトで日本語力を磨くこと10ヶ月。韓国に帰国後、日本語を使う仕事に絞って就職活動を行うも、思うようにいかない日々を送っていたなかでTYPICAから内定を獲得したソイの“現在地”とは。(文中敬称略)

異色だったTYPICA
「対面で面接ができないのであれば、採用できません」
コロナ禍により、日本への渡航が認められていなかった2021年9月。最終面接まで進んだ日本の企業からそう告げられたとき、ソイは肩を落とさずにはいられなかった。
努力でどうにかできる問題ではない。だが、ソイはその原因を自分自身に求めていた。
私には無理かもしれない、というネガティブな心情が表に出ていたのだろうか。それまでも、最終面接まで進んだ企業はいくつかあったが、内定に漕ぎ着けたところは一社もなかった。
「日本企業の外国人部門ではなく、マイナビとリクナビで就職先を探していたのは、国籍にかかわらず、みんなと一緒に働きたいと思っていたからです。本当のところはわからないけれど、私を採用するとビザの発行が必要だったりと面倒なことが増えるから、企業は日本の学生を選んだのかなと想像していました」
2020年9月に就活を始めてから1年が経とうとしていた。暗中模索の日々が続くなかで、ソイは自身への信頼も失い始めていた。どこの会社でもいい、どんな仕事でもいいから働きたい。切羽詰まっていたソイは作戦を変更し、「日本企業の韓国部門」での募集に活路を求めた。
そんなときに出会ったのがTYPICAだった。一次面接を担当したメンバーから、「(あなたのことは)説明会で見たよ。覚えてるよ」と気軽に声をかけられたとき、ソイは救われたような気持ちを抱いていた。
「ホームページを見たときや説明会に参加したときにも感じたのは、いい意味で会社っぽくないということ。うまく言えないけれど、『会社ではなくTYPICA』というふうに私の目には映ったんです」
代表の後藤との最終面接では、さらに印象的な経験がソイを待っていた。
「私が会社の戦力になるかどうかではなく、どういう人間なのかを見られているように感じました。記憶があいまいなのですが、後藤さんから『用意した答えではなく、あなたが本当に思っていることを話してね』と言われたときはハッとしたんです。
そこで『就活生』ではなく『私』として話すように切り替えたものの、手応えは全然なかった。だから、合格通知が来たときは喜びより驚きの方が断然大きかったですね」

自分との約束を果たす
韓国で生まれ育ったソイが日本に興味を持ったきっかけは、韓国で放送されている日本のTVドラマ「孤独のグルメ」と「深夜食堂」だ。
いずれも市井に生きる人たちの人生模様を「食」の切り口から描いた作品である。もともと食べることが好きだったソイは、その素朴で飾らない世界観の虜になった。
ドラマの世界により深く入り込みたくて、ソイが登場人物のセリフを書き写すようになったのは大学3年生の頃。心のおもむくままに、ソイは日本語を身につけていった。
やがて日本語を使った仕事をしたいという思いが芽生えたソイは、大学4年の春、交換留学の制度を活用し、日本にやってきた。
留学前、ソイは「絶対に親から仕送りをもらわない」という約束を自分自身と交わしていた。自分で決めたことは、人に頼らずに自分の力でやりきるもの。ソイにとってそれは、ごく自然な発想だった。
心中ひそかな決意を抱いたソイは、日本に来てすぐ、外国人でも働けるアルバイトを探し始めた。「自分でお金を稼ぎ出す」ことが目的である。職種や仕事内容にこだわるつもりはなかった。選んだのは、東京・渋谷のロフトだった。
日本で過ごした10ヵ月間は、「慌ただしかった」という記憶に包まれている。1ヶ月に10万円ほどを稼ぎながら、大学の課題もこなす日々のなかで、余暇を楽しむ暇はなかった。レポートの提出期限が迫った時期など、2日連続の徹夜は当たり前、最長で4日連続で徹夜しながら目の前のハードルを乗り越えていった。
だが、身体は正直である。大学で過ごす時間は、ふいに襲いかかってくる睡魔との闘いを強いられた。ひとたび机に突っ伏したが最後、深い眠りの中に連れ去られてしまうのだ。授業の合間にある10分間の休憩中に爆睡し、慌てて教室を移動したことは何度もある。
「今思えば、やりきらなきゃいけないという一心だったことがよかったのかもしれません。体力的にはきつかったのですが、日本語のレパートリーがどんどん増えていく喜びが上回っているところもありましたね」
留学中、「絶対に親の援助を受けない」という決意を知らせなかった両親からは、毎月仕送りが振り込まれていた。だが、自分との約束を果たしたソイは一切それに手をつけず、帰国後、両親に全額返したのだ。
「お金を受け取った母は、何も言わずに泣いていました。両親から『頑張ったね』と言ってもらえたとき、すべての疲れが吹き飛んでしまうほどうれしかったんです」

人にしかできない仕事がしたい
ロフトでのアルバイトは、好きで選んだわけでもなかった。だが、「仕事の喜び」を教えてくれたのはそこで過ごした日々だった。
外国人旅行客に対応する免税カウンターで働いていたソイが、周囲から一目置かれるようになったのは入社3ヶ月後のことだ。飲み込みが早かったソイは、数をこなすうちに、他の追随を許さないほど速くラッピングするスキルを手に入れていた。
数人のスタッフが並ぶ免税カウンターで、ソイのところだけ客がどんどん流れていくのは誰の目にも明らかだった。その華麗で俊敏な手さばきを見た客から感嘆まじりの笑い声が漏れたこともあれば、「あなたは最高だね!」と賛辞を贈られたこともある。
「私も何かお返ししたくて、それぞれの国の言葉で『ありがとう』を伝えるようにしたら、もっと距離を縮められたんです。自分がやったことで誰かの役に立てている、その感覚は私の心を満たしてくれました」
ロフトで勤務した10ヶ月のうちに、ソイは周囲から必要とされる存在になっていた。「辞めて韓国に戻る」と告げたとき、フロアの店長からは「(社員に登用されることを)期待していたのに…」という言葉をかけられた。アルバイト仲間からも「シンさんなしでそうやっていけばいいの?」という不安の声があがった。
「とにかく人と話すことが楽しい」というソイのなかに境界線はなかった。建物は別だが、同じ休憩室を使用する西武百貨店のスタッフやゴミ捨て場の管理員も、ソイにとっては話し相手だった。
「そういう人たちにも挨拶する私を見てアルバイト仲間は驚いていたけれど、私には特別なことをしているつもりはなかった。会うたびに挨拶しているうちに、『今日も来たの?』と声をかけられたり、お菓子をもらったりと、少しずつ関係性が発展していくのも楽しみのひとつだったんです」

そんなソイのキャラクターは、大学でも健在だった。約120名の学生が所属する法学科には、模擬裁判や教授との交流会など、年に何度か開催される恒例行事があった。原則として全員参加なので、そのイベントを企画運営する委員会のメンバーは調整力やコミュニケーション力が求められた。
浪人して入学した年上の同級生は、どうやらとっつきにくい存在だったらしい。「あのお姉さん怖い」「話しかけづらい」と距離を置く他のメンバーから「ソイちゃん行ってきて」と頼りにされることが多かった。
「私はいろんな人に話しかけたいし、話ができないのならせめて挨拶だけでもしたいんです。逆に目が合っても挨拶をしないなんて、私には理解できない。道端ですれ違った人にはさすがにやらないですけども(笑)」
分け隔てなく人と付き合えるのはソイの天性でもある。それが発露したのは、小学校4年生のときだ。
ソイのクラスに、誰とも挨拶すら交わさない女子(以下、A子)がいた。A子の存在を無視できなかったソイは、ある日、「なんでいつも一人でいるの?」と声をかけた。それをきっかけに、A子との距離は少しずつ縮まっていった。
そんなソイの行動は、まわりの空気をも変えていく。当初は「なんであの子と話をするの?」と遠巻きに見ていたソイの友達も、いつからかA子と話すようになった。5年生になる頃にはもう、A子と周りを隔てていた壁はきれいさっぱりなくなっていた。
「A子はきっと、一人でいたかったのではなく、誰かが話しかけてくれるのを待っていたんだと思います。卒業式の日、彼女から『あのとき、ソイちゃんが私に話しかけてくれたおかげだよ』と言われたことは、いまだに忘れられません。別々の中学校に進んでから15年ほど経った今も、彼女とはつながっているんです」

いつの間にか、変わっている
韓国の芸術高校でヒップホップダンスを専攻していたソイは、大学の法学部という異色の進路を選択した。
「まわりは皆、芸術系のことしか眼中になく、社会問題や文学、科学には疎い人ばかり。狭い世界に留まっていたくない、もっといろんなことを知りたいという思いから、先生に勧められた法学部を選んだんです」
そんなソイがまだ知らない世界を求めて日本に渡り、日本語を体得していった先で出会ったのがTYPICAだった。だが働き口を得て喜んだのもつかの間、ソイは入社後すぐに壁にぶち当たっていた。
「日本チームや台湾チームのコミュニティマネージャーは、私と同年代だけど、他の会社でキャリアを積んでいてパフォーマンスも高い。かたや私は新卒で、スキルも経験も不足している。自分に足りないところばかり目について、自信が失われていく感じがあるんです。
でも、就活時のようにお先真っ暗という感覚はありません。彼らから力をもらっているところもあるし、答えをすべて知っているような後藤さんと話していると、ここなら成長できるという確信を持てる。KPIについても、達成しなければどうしようという不安ばかりが先に立っていたけれど、徐々にどうすれば達成できるかを考えられるようになっています。
それに、ロースターさんから毎回『ありがとうございます』『一人で大変だろうけどお疲れさま』と声をかけてもらえると、がんばろうという気持ちが湧いてきます。最近は、『ついに生豆が届きました。お疲れさまです。次回お店に来られたら、一緒にコーヒーを飲みましょう』というメッセージをもらって、報われたような気持ちになりました」
とはいえ、加速度的に成長している創業3年目のTYPICAでは、クリアしなければならない課題が山ほどある。
「コーヒーにも詳しくないですし、今はいっぱいいっぱいなので目標はありません。でも、頑張ればできるようになるという未来は信じられるんです」
その鍵は、ソイがお守り代わりにしている「いつの間にか」という言葉にある。
「目の前のことを一生懸命頑張っていれば、いつの間にか目標を達成できたり、大事なものを手に入れられたりすると思うんです。
私のこれまでを振り返ってみても、孤独のグルメや深夜食堂を見始めたときは、日本で留学するとは思っていなかったし、ましてや日本語を使った仕事をするなんて想像だにしなかった。
日本語を勉強し始めたこと、日本に交換留学に来たこと、一日中日本語でコミュニケーションをとるようになったこと、TYPICAに入社したこと、韓国部門でひとりで仕事をしていること……。そのどれもが『いつの間にか』やっていたことなんです。
人間関係だって同じです。今はコロナの影響でロースターさんとは電話で話すことが多いけれど、顔を見て話せるだけで私はうれしい。仲良くなりたくて話しているわけでもなく、話しているうちにいつの間にか仲良くなっている、という感覚です。人間関係をどんどん深めていけるし、その過程で知らなかった世界にも触れられる。それが今の仕事のおもしろいところです」
どれほど練られた戦略も、どれほど磨かれたテクニックも、本当の心には敵わない。そう証明してきたソイなら、いつの間にか、TYPICAには欠かせない存在になっているだろう。
写真:パク・ジウ