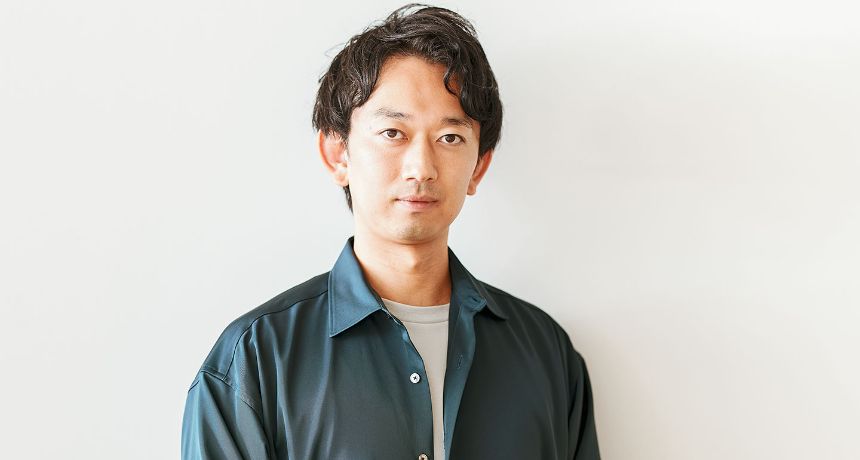関わるみんなを幸せに。現実感ある理想を追って
TYPICAには、コーヒー業界での経験が豊富な人材が集うコーヒーエキスパートチームがある。そのメンバーのひとりとして、品質管理と大手、中大手コーヒー企業とのコミュニケーションを担当しているのが永井和人だ。
キャメル珈琲で働いた13年間の中では、主にコーヒー生豆買付と品質管理を担当。生産地と消費者を結ぶコーヒーシリーズ等、新商品開発にも携わった。同社でそれなりにやりがいを感じながら仕事をしていた永井がTYPICAに転職した背景には、既存のサプライチェーンに対する払拭しがたいジレンマがあった。

誰かが不幸になるのが嫌だった
ひとくちに生産者と言っても、置かれている境遇には大きな隔たりがある。大農園の経営者は裕福な生活を送っていたとしても、そこで働く従業員が豊かな暮らしをしているとは限らない。小規模生産者に至っては、日々の生活すらままならない場合もある。
だからといって買い手が彼らの望む価格でコーヒーをむやみに買うわけにはいかない。それにより店頭での販売価格を上げると、自社のコーヒーを楽しみにしてくれている生活者の購入のハードルが上がる。資本主義社会で生きている限り、そのメカニズムから逃れることはできない……。永井は前職にて長年、そんなジレンマにさらされてきた。
「生産地と消費者を結ぶコーヒーシリーズといった高付加価値商品の開発をしたり、生産者も消費者もサプライチェーンの両岸が常に納得できるにはどうしたら良いかを考えていました。でも、生産コストに関係のない相場の変動でもオファー価格は上下するし、それに左右されて小売業者どうしでの競争も起こる。自分の中でスッキリする答えは見つけられなかったんです」
サプライチェーン全体をもっと効率化できれば、なるべく原価に近い値段で消費者に提供し、生産者も消費者も喜ぶ形がつくれるんじゃないか……。そんな思いが沸点に達した永井は2020年、13年働いたキャメル珈琲を離れ、流通にまつわるムダ・ムラ・ムリの解消に挑む食品系の会社(A社)に転職。商品開発プロジェクトに携わったのち、TYPICAに入社した。
「詳細な顧客データを収集してマーケティングに生かすDXによって、確度の低い発注による食品廃棄や、店頭に並ばない新商品開発をなくそうとする。ただそのためには仕入れ先のメーカーさんに値下げをお願いしないといけなかったりと、いろんな協力がなければ成り立たないと思い知らされました。そんな中でも、サプライチェーンを効率化して最終価格も抑えられるビジネスモデルがあると知ったことはいい学びでしたね」

多様性を愉しめるコーヒー
コーヒー生豆の取引は、感情や人間関係に左右されるところが大きいウエットなビジネスだとよく言われる。農作物であるコーヒーは収穫量や品質が不安定であるうえに、先物価格の変動が激しいため、人と人の信頼関係やつながりによってそれらが担保される側面もあるからだ。
「12年前、ブラジルで資格を取るために一緒に学んでいた生産者の人と、最近久しぶりに会ったんですよね。僕も彼も顔は変わっていたからすぐにはわからなかったけれど、いろいろ話をしているうちにお互い記憶がよみがえってきて。彼から『コーヒービジネスに戻ってきてくれてうれしいよ』と言われると感慨深かったし、おこがましい言い方かもしれないけれど、何か貢献できることがあればと思う気持ちが自然に湧いてきたんです。
コーヒーが特別だと思うのは、その価値や美味しさは、生産者の人柄や思想哲学、生き方、仕事への取り組み方にも影響されるところ。バイヤーとして生産地に行き、生産者と交流していたからでもありますが、生産者がこの土地に合っている品種を選んだ、今回新たな精製方法に挑戦してみた、環境のことも考えて取り組んでいる……等々の背景を含めたすべてが美味しさにつながるんです。
SCAも近年カッピングスコアだけじゃない評価方法を提唱していて、スペシャルティコーヒー業界の共通認識になっていくのではないかと思います。だからこそコーヒーは、他の食べ物や飲み物と比べて嗜好の範囲がかなり広いんじゃないかと思いますね」

そう語る永井だが、コーヒーに目覚めたのはキャメル珈琲に入社した後のことだ。2009年、パナマのゲイシャを初めて飲んだとき、世の中にはこんなに美味しい飲み物があるのかと衝撃を受けたのだ。
入社前はカフェにもほとんど行ったことがなく、産地や品種によってコーヒーの味が異なることも知らなかった。あったのは、コーヒーの仕事はかっこいいという漠然とした憧れくらい。「食べるのが好き」という理由から食品に関わる仕事を探していた中で、縁があったのがキャメル珈琲だったのだ。
一方、面接をした担当者は、明確な理由をもって永井を採用していた。永井は入社後、上司となったその社員から採用理由について聞かされた。
「コーヒーの味の違いを感じ分ける能力は、入社後でも磨いていける。一番大事なのはいろんな食べ物を食べてきた経験がつくりだす味の引き出しであって、それは後からじゃ身につけることができない」
思えば、子どもの頃から親が食べている珍味をつまみ食いしたり、抹茶やコーヒーも好きこのんで飲んでいた。好き嫌いはあったが、いわゆる食わず嫌いはせず「食べる?」と訊かれたらまずは食べてみる性格だった。
大学時代は、いわゆる食べ歩きに多くの時間と金を注ぎ込んだ。スープカレーにハマった時期は、チェーン店から個人経営の小さな店まで、店舗形態や知名度にこだわらず、多くの店をまわった。
「とにかくいろんな店にいくのが好きでした。好きな味を見つけるというよりは同じ料理でもいろんな味がある、もっと言えばこないだ来た時とちょっと味が違うなというふうに、違いを感じ分けることを愉しんでいたんです。多様性を楽しみたいのか、未知のものにチャレンジしたいのか、単に飽き性なだけなのか……。いずれにせよ、特定の店や味に思い入れを抱くタイプではなかったですね」
そんな習慣は、図らずも仕事において役立った。ブレンドの味を維持する役割を担っていた永井にとって、自分の主観や好みは抜きにして、感じた味をそのままの形で記憶に取っておく──生産地でカッピングしたコーヒーの味を、点数やフレーバーコメントだけでは収まりきらない記憶として残しておくスキルはきわめて重要だったのだ。

夢物語だと思い込んでいた
TYPICAは2024年8月、ニューモデルをローンチした。その目玉機能のひとつが、世界中のコーヒー生産者に調達リクエストを公開するウィッシュリストだ。買い手は希望の品種、精製方法、価格などを登録すれば、パーソナライズされたオファーが生産者から届く仕組みである。売り手と買い手の情報の非対称性を解消し、対等で透明な取引を実現しうる可能性を秘めている。
「IT技術を使って需要データを生産者にそのまま届けるという意味では、サプライチェーンを最適化してムリ・ムダ・ムラをなくすことができる。加えて、VCや投資家から出資いただいて業界の構造を変えていく挑戦をする……。既存の枠組みにとらわれないアプローチをとる会社だという印象は、入社前も入社後も変わっていません。
生産者やロースター、生活者、もっと言えば輸出業者や倉庫業者も含めた、サプライチェーンに関わるみんなが納得できる世界をつくりたい。前職時代からそう思い描くことはあったけれど、理想論なんだろうなという自覚はあったんですよね。
でもTYPICAならその理想を追い求められるし、現実に近づいている実感を得られます。スペシャルティコーヒーという概念が日本に輸入されてから約20年経って、スペシャルティがコーヒー市場で一定のシェアを確保するようになったものの、まだまだ成長の余地はある。TYPICAならその起爆剤になれそうな気がしています。ただ、今振り返れば、キャメル珈琲でも自分が主体的になってサプライチェーンを変えようと取り組めば、また違った結果になったのかなと」

とはいえ、中・大手ロースターとの商談では一筋縄ではいかないことの方が多いのが実情だ。本当に安定供給できるのか、何らかの事情で想定していた品質と量のコーヒーが手に入らなかった場合、替えはきくのか、といったリスクの方に目が向き、今までのやり方と違う、うちのスタンスと違うといった消極的な反応をもらうことも少なくない。
「解決策が一律にあるわけじゃないので、まずは各企業さんの問題意識をしっかりヒアリングすること。それと同時に、リスクをとってでも理想を実現したい、革新してきたいという主体性を持ってもらえるように働きかけていく必要があると思っています。
コーヒーは農作物なので、リスクは常に付きまといます。買い手側からすれば期待した品質のものが来ない、売り手側からすれば期待した量が売れない、物流面では期日通りに船が港に到着しない等々。そういう問題はよく起こるのですが、信頼関係によって支えられた透明性あるダイレクトトレードなら、問題の原因を明らかにして改善に結びつけていけると思うんですよね。
成功事例がない状況では二の足を踏みたくなるものだからこそ、ダイレクトトレードによってどういう世界が開けるのかを事例として共有することで、一歩踏み出そうと思う企業さんを増やしていきたいと思っています」
たとえば月に行きたいとして、ロケットの存在を知らなければ、それは叶わぬ夢物語に感じるだろう。しかし、月に行くためにロケットを飛ばす実験を重ねている人たちがいると知ったとき、それは現実味を帯びた理想へと変わってゆく。前職でどれだけジレンマを感じても、それを解決する術を見つけることを諦めなかった永井にとって、TYPICAはロケットのような存在ともいえるのだ。
「(TYPICAが掲げる)アラビカ種の33%を自社プラットフォームで流通させる目標って、普通に考えたら突拍子もないですよね。でも叶うか叶わないかを考えるよりも、叶えられそうな方法があるならやることが大事かなと。だから僕自身、理想とは言いつつも、現実感があるというか、実現できると思っているからTYPICAで働くことを選んだんでしょうね」