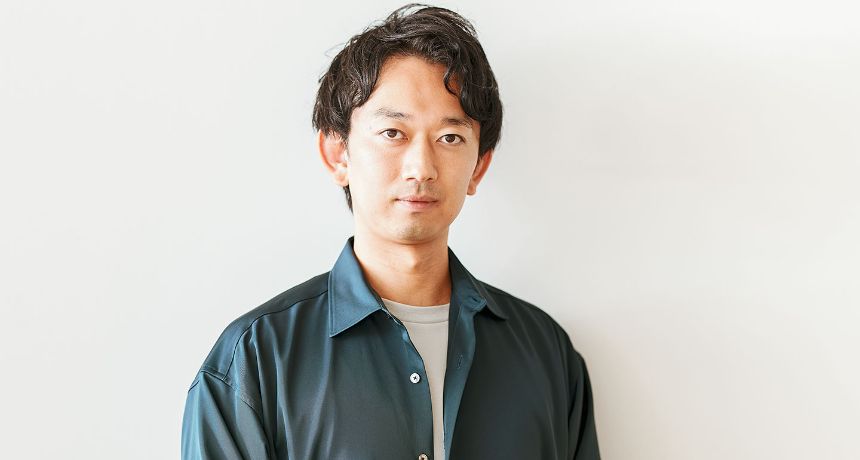見えてる以上に世界は広い。今・ここ・すべてが学びの機会
17歳のときにバリスタとしてコーヒーの仕事を始めてから約7年間で、ヘッドバリスタ、品質管理マネージャー、生豆の買付、スペシャルティコーヒー協会の認定トレーナー、スペシャルティコーヒー&ワインバーの運営などを経験。それでも飽き足らず、コーヒーのサプライチェーンのすべての側面に携わりたいと、2024年10月にTYPICAに入社したのが、ベネズエラ出身のハビエル・ヘルシだ。
現在24歳、倍速の人生を生きてきたようなハビエルの目標は「コーヒーチェーンのすべてをつなぎ、世界にとって特別なものにすること」。その目標をより具体化するためにも、日々試行錯誤を続ける彼は、新たな環境でも進化を止めることはない。

ひと味違う会社だった
ハビエルがTYPICAの存在を知ったのは、マドリードのオラコーヒーで品質管理マネージャーとして働いていたときのことだ。TYPICAで働くサミュエルの対応が的確かつ誠実だったことから、好印象を持っていた。
一方で、注文すればすぐに生豆が届く一般的な輸入会社とは異なり、到着予定日から遅れるケースが多いことに疑問を感じていた。上司に聞くと「TYPICAは違うメカニズムで動いているからね」と説明してくれた。やがて生産者と足並みを揃えて仕事をしているのだという理解に至ったときは、目を見開かされたような感覚があった。
生豆の輸入会社に絞って新たな活躍の場を探していたハビエルの中で、TYPICAはひと味違う存在に映っていた。Webサイトを開けば、各生産者の写真やナラティブが掲載されている。単なるPR素材にとどまらない奥行き──その背後にある結びつきや哲学を感じ取るうちに、興味はおのずと膨らんでいった。
それから数年。友人から「TYPICAが人を募集している」という知らせを受けたハビエルは迷いなく応募を決めた。コンフォートゾーンを飛び出して新しい環境や仕事に挑戦できる、と思えば胸は自然と高鳴った。

物事には必ず両面がある
これまでの経験を活かせる品質管理を担当するつもりでTYPICAに入社したハビエルだが、コミュニティマネージャーの役割も担うことになった。いわゆるセールス的な仕事は未知の領域だが、その展開をネガティブには捉えなかった。むしろ冒険要素が強まったことに、アドレナリンが湧き出ていた。
一方で、ヨーロッパチームのメンバーが4人しかいなかったことには驚いた。事業内容からしても、外から見えていた印象からしても、もっと規模が大きいイメージがあったためだ。
だが、変わらずハビエルは前向きだった。さまざまな業務にかかわり、他のチームをサポートしなければならない場面も多いが、そのダイナミックさをむしろ刺激的と捉えてきた。
「どの会社も独自の組織体制やスタイルがあると思うので、組織的か/組織的じゃないかといった評価は必要ないと思います。スタッフが少なくて、チームの枠組みを超えて働く必要があるのなら、それは自分の成長のためにも受け入れるべきこと。
僕は普段から、コップに半分入っている水を“半分しかない”ではなく、“半分ある”と考えるようにしています。7年ほど過ごしたスペインを離れて、アムステルダムに引っ越したのも、この会社での挑戦に賭けているから。慣れない環境で慣れないことに取り組む方が学びも大きく、そのスピードも早まりますからね」

何にしたがって生きるのか?
ハビエルは子どもの頃から常に、人と違うことをやりたいと考えているところがあった。高校卒業を間近に控えた2017年、17歳のハビエルはベネズエラの首都・カラカスのカフェでバリスタとして働き始めた。
しかし、弁護士やエンジニアなどのメインストリームからは遠く離れた仕事である。友人からは「バリスタかよ」とからかわれることもあり、自分の選択を信じきれていなかった。
深刻な国内の経済的、政治的危機により、家族とともにスペインへ渡ったのは翌2018年のことだ。ハビエルはマドリードの大学に入学し、法律と経済について学び始めた。
大学で勉強に励みながらも、ハビエルはコーヒーの世界にのめり込んでいった。バリスタとしてコーヒーを淹れることで得られる「自分が手がけた」という満足感が大きなご褒美だった。
その後、知識と経験を蓄えていき、人に教える立場になると、コーヒーの世界は魅力が増した。相手が学んでいると同時に、自分も何かを学んでいる。その感覚に連なるように、もっと広く学びたいという好奇心や野心は募るばかりだった。
一方で、ハビエルは人知れず内なる闘いを続けていた。コーヒーの仕事は人から軽く見られるうえに、自分をインスパイアしてくれるロールモデルとして尊敬する10歳年上の兄は弁護士として働いているのだ。家族や周囲の人々の期待を裏切ってはいけない、という重圧に心は縛られていた。
それが和らいだのは、講習でコーヒーの濃度を測定する手法を学んだときだ。バリスタは単にコーヒーを淹れるだけの仕事じゃない。これは科学とも関わっていて、多くの人に知られていない奥深さがある──。そう気づいたとき、コーヒーの世界を追求し続けてもいいのだと許されたような感覚があったのだ。
それでも、すべてを投げうってアクセルを踏み込むほどの覚悟には至らなかった。法律家の道へ進むか、コーヒーの道へ進むか。心の奥底ではどちらを選びたいかをわかっているのに、頭のどこかからはそれを阻む声が絶え間なく響いてくる。大学をやめて“不真面目”な道に進めば、まわりに恥ずかしい思いをさせてしまうぞ。おまえは家族の期待を裏切ってまでコーヒーをやりたいのか……。そんな葛藤に、ハビエルの心は引き裂かれていた。

決断のとき
決断の日が訪れたのは、大学1年のときだ。法学の期末試験に備えて勉強に励んでいたハビエルは、その試験が実施される日、カッピング会があることを知る。
デンマークのロースターがマドリードにやってくる、めったにないチャンスだった。自分が学びを得て成長するだけでなく、そこに集まる人々との繋がりも得られるのだ。
とはいえ、その試験で単位を取得できなければ、多くの科目を再履修しなければならない。それは1年間を棒に振ることを意味している。コーヒーへの情熱、本気度が試されていた。
結局、ハビエルが肚を決めたのは当日の朝だった。カッピング会の最中、大学からは「試験を受けていないため、あなたは自動的に不合格になります」というメールが届いていたが、ハビエルはコーヒーをすすりながら自分の決断が正しかったことを確信していた。
といっても、そのカッピング会で人生を変えるような出会いがあったわけではない。何かに目覚めるビッグバンが起こったわけでもない。期末試験を受けずに、ごくありふれたカッピング会に参加した事実だけ見れば、100人中99人が愚かな選択だと言ったかもしれない。
だがハビエルにとって、そんなことはどうでもよかった。固定観念や誰かの声を振りほどき、自分の内なる声にしたがって決断を下したこと。それが何よりの成果だった。
その後、大学を退学することを働いていたコーヒー店のオーナーに報告した際、「なんで自分の人生を台無しにするんだ? 卒業して挽回すべきだ」と叱咤された。だがハビエルは「そうは思いません。好きなことを軸に、自分なりの方法で人生を組み立てます」と宣言した。燃えるような決意の裏で、退路を断った恐怖と焦燥が、ハビエルを駆り立てていた。

全体像を見ているのか?
それから歩んできた道のりは、有言実行そのものだった。コーヒーの世界でどんなキャリアを積んでいきたいのか。自分なりに描いた青写真にしたがって、ハビエルは毎年のように新しい仕事や役割に挑んできた。ヘッドバリスタ、品質管理マネージャー、生豆の買付、コーヒー農園での精製アシスタント等々、これまで約7年のうちに経験してきた仕事はすべて目標から逆算して立てた計画に基づいている。
「僕は何かを達成したとしても、そこで満足できない性格です。学び続けたい、変化し続けたいという気持ちが時に強すぎるくらい強いんです。コーヒーも、ただ飲み物として美味しく淹れるだけじゃ全然物足りない。その分野について広く横断的に知る方が価値を生み出せるし、業界全体を押し上げていく推進力になるからです。トゲのある言い方に聞こえるかもしれないけれど、僕は凡庸が嫌いなんです」
ハビエルにとって、学び続けることの目的は、誰かに価値を還元することにある。教育の仕事では自分の知識を誰かに共有し、品質管理の仕事では顧客の信用を裏切らないように、品質を守り続ける。それが自分の幸せであり喜びだった。

TYPICAに入社後は、そこに「この状況に関わるすべての人にどんな影響を与えるのか」という思考が加わった。そのきっかけが、コミュニティマネージャーの藤原麻緒との対話だった。入社直後、あらゆる提案に対して、彼女から「そうだね。それも一つの方法だけど、まず全体像を見なきゃいけないんじゃない?」と問われたとき、ハビエルはただただ混乱していた。
「彼女の言っていることがまったく理解できなかったんです。帰宅して頭を整理して新しい視点を持ったうえで、話し合いに臨んだ翌日も『もっと大きな視点で見なきゃ。◯◯と◯◯と◯◯、全部がそれに影響しているから』と同じような指摘を受けた。頭を殴られたような衝撃があったんです」
自分に足りないものは何なのだろう……。そのことばかり考え続けた末、開眼する瞬間はふいに訪れた。自宅で恋人の話を聞いていたとき、どこかから「君は全体像を見ていない」という声が聞こえてきたのだ。そうか、こういうことか。自分では見えているつもりだけど、本当はごく狭い視点でしか捉えられていないんだ。鳥肌が立つほどの衝撃に、ハビエルはひそかに熱狂していた。
「それからは、できるだけ物事を360度の視点から見るように心がけています。僕たちは常に、自分ひとりで何かを生み出すことはできない。他の存在と影響を与え合いながら生きていますからね」

コーヒー生産者に声を与える
コーヒーとワインはよく同じカテゴリーで語られるが、コーヒーは遅れているという見方も少なくない。ワイン業界では、地域ごとの特性や生産者の哲学、ストーリーを重要視する考え方が消費者にも浸透している。かたやコーヒー業界では、消費者だけでなくバリスタやロースターでも、それらを認知していないことが一般的だからである。
ワインバーを経営していたハビエル自身、その違いを身をもって体感した。
「コーヒーがどこから来たのかを本当の意味で知っているバリスタはほんの一部しかいない。彼らは目の前のコーヒーが生産された国の名前は知っていても、どんな人たちがどんな思いでつくっているのかは知らない。いわゆる『最小限の介入』と呼ばれるアプローチで、生産者のストーリーやテロワールをそのまま表現することを重視するワインのように、コーヒーについてももっと具体的に語るべきだなと。それがトレーサビリティについて考え直すきっかけでした。
僕が人生で成し遂げたい目標は、コーヒー生産者自身が声を持ち、価格決定権を持てる環境をつくること。そして、すべての生産者が重要な存在だという認識を広めること。その手段として、自分たちは前面に出ず、生産者とロースターのつながりをお膳立てするTYPICAは、最適だと思えたんです。
と同時に、ロブスタ種にもスポットライトを当てていきたいと思っています。ロブスタはコーヒー生産量のうち約40%を占めているけれど、『病気に強く量産できるが、品質は低い』という固定観念のせいで、スペシャルティの世界ではほぼ知られていません。でも、適切に精製され、実験的なプロセスが施されると、驚くほど素晴らしい品質のコーヒーができることを僕は実体験として知っている。そういう個人的なミッションを、TYPICAでの仕事とうまく組み合わせていきたいと思っています」