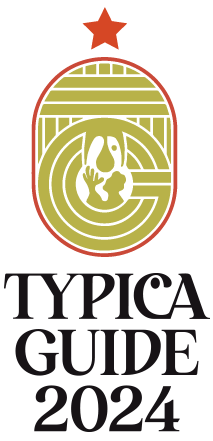

こだわるよりも大事なことを。“商売人”の一途な思い

古家章司さんが経営するThe Coffee Marketは、大阪・天王寺エリアに3店舗を展開している。豊富なケーキメニューを揃える焙煎・ケーキ工房、世代を超えてくつろげるカフェをコンセプトにした145、シュークリームや焼き菓子を提供する+ BAKES。店舗ごとに特色は異なるが、いずれもコーヒーが軸となっている。
焙煎豆の卸販売からキャリアをスタートした古家さんは、喫茶店ブームが去った後に店を構えて以来30年以上にわたり、コーヒーや業界の人々と向き合ってきた。
「しんどいけど年々楽しくなっている」カフェの経営についてそう話す古家さんに、その理由や今後の展望を聞いた。(文中敬称略)

「感謝」の気持ちに支えられて
The Coffee Marketの各店舗のインスタグラムを開けば、パスタやベーグルサンド、シュークリーム、ケーキなど、多種多様なフードメニューが目に飛び込んでくる。特に全てパティシエたちの発案によるオリジナルのスイーツは、一見専門店かと見紛うほど本格的なラインナップだ。

だが、主力はあくまでもコーヒー。店頭では客の幅広い嗜好に応える豆を10種類以上そろえ、ハンドドリップからエスプレッソ、カフェラテにアフォガード、コーヒーフロートまで、さまざまな楽しみ方を用意している。
「コーヒーを飲みに行った時にお菓子があると嬉しいでしょ。それが美味しかったら、ああええな、と思うし。自分がお客さんとしてそう感じるから」
お客さんに満足してもらえることが何よりも大事、という古家の姿勢は店づくりにも表れる。
「流行っている店やチェーン店、味を売りにしている個人経営の店など、飲食店であれば行けるところには行きます。お客さんやスタッフから勧められた店にも足を運ぶのは、その店のいいところを同じように感じてみたいから。店をやるからにはまずいと思われるものは出せないでしょう。お客さんの反応を見ながら焙煎もしょっちゅう変えますね」

The Coffee Marketは、各店舗がいずれも徒歩圏内にある。一番遠くても徒歩15分。客の中には、1日に2,3回来店する常連や、店舗をはしごする人もいるという。
「移動先の店舗で、同じお客さんに会うこともある。気まずいと思われているかもしれないけれど、私としては表彰したいくらいです。そういう方を見ると何かプレゼントしたいなといつも思う。感謝の気持ちを伝えないと申し訳ないなと」
感謝されることの喜び。その実感は深まる一方だ。
「お金をもらって感謝してもらえるってすごい商売やなと感じます。『ええ店や、居心地よかったわ』って言ってもらえたら嬉しいし、やっててよかったなと思う。楽しさは増してますね。焙煎にしてもコーヒーを売ることにしても、経営にしても」


喜んでもらうことが最優先
そう語る古家だが、もともと飲食店を経営する気はさらさらなかった。経営する喫茶店が借金まみれで喧嘩が絶えない両親の姿や、一人で店を切り盛りする母の苦労を目の当たりにしていたからだ。
一方で、コーヒーは憧れの存在だった。1970年代の純喫茶ブームを肌で感じながら育った少年時代の古家にとって、喫茶店は大人の階段を一足飛びで上れるような場所だったのだ。
「カッコええ飲み物じゃないですか。初めて喫茶店に行く時は、何をどう注文していいかも分からないから事前に練習しましたよ。とにかく店の人が来たらアメリカンって言おうと、それだけ決めとったんですよ」
そんな業界で焙煎士として働く父の背中を見て、次第にコーヒーの世界に惹かれていった。

食品会社で卸売業務を担当した古家は、「同じ卸ならコーヒーの方が面白そう」と、コーヒー豆の焙煎や卸売を行う美鈴コーヒーに入社し、喫茶店を顧客とする営業マンになった。
すでに斜陽だった業界に、「喫茶店でビル一棟が建つ」と言われた時代の面影は見当たらなかった。ドトールコーヒーに代表される、セルフサービスカフェの台頭により、店をたたむ個人経営の喫茶店が相次いでいた。同じブレンドコーヒーで比べると、1杯350〜400円の喫茶店に対して180円のドトールコーヒー。安価で手軽に飲める美味しいコーヒーに人々は引きつけられていった。
そんな中で一世を風靡したのがゲーム喫茶だった。客寄せ目的でゲームテーブルを設置し、経営を立て直そうとする喫茶店が急増したことで、業界の衰退はさらに加速していったのである。

古家の顧客の中でも、業界の未来に希望を抱けず、モチベーションを失いかけている喫茶店のマスターが大半だった。だからといって、業界に見切りをつけたいという気持ちは芽生えなかった。
「喫茶店は絶対世の中に必要なものだし、利益率が高くて儲かる商売だとも思っていました。スイッチの切り替えができたり、おしゃれな気分になれたりする、そういう喫茶店の雰囲気も好きだった。何よりマスターとのやりとりが楽しかったんです」
逆風の中でも美味しいコーヒーを提供しようというスタンスを崩さないマスターもいた。当時、世間はバブル真っ只中。喫茶店以上に待遇の良い職場はいくらでもあった。慢性的に人手が足りない中で売り上げをつくる戦略を考える必要に迫られていた。
どうすれば儲けてもらえるか、どうすれば喜んでもらえるか。その一点に集中していた古家の関わり方は、営業マンの枠を超えていた。ランチメニューのアイディアを提供したり、近隣の飲食店の情報を共有したり。時にはキッチンに入って皿洗いをすることもあった。

なかでも効果を発揮したのが、人手を浮かすためにコーヒーマシンを利用するという奥の手だった。「マシンで淹れても美味しいコーヒーを持ってきますから、コーヒーは私に任せてください」そう言って目の前で実演し、味見する機会をつくったが、相手は「個性溢れる」マスターだ。簡単に「はい、そうですか」と首を縦に振るような人たちではない。
「昔の人はえげつなかった。わざと怒鳴りつけて、自分がコーヒーにこだわっていることをアピールしてくるんですよ。『こんなコーヒー飲まれへんやないかい、もっとええのん持ってこい』とね」
それでも「そんなやり取りが最高におもしろかった」と古家は懐かしむ。
「そこを乗り越えた時に、繋がりが一層深まるんです。特にガツンと言ってくる人ほど、その傾向が強かった。もしかしたら子どもの頃、親が厳しくて褒められることがあまりなかったからかもしれない。ある種そういうのに飢えていたというのかな。困っているお客さんをお助けして感謝されることがすごく心地よかったんです」

やがて美鈴コーヒーの大阪事業所が撤退することになり、無償で事業を譲り受けた。当初は同社から焙煎したコーヒー豆を仕入れ、卸売を行っていたが、その後父親の会社を吸収合併。1992年、29歳でカフェの一号店を開店した。
数年経つと、焙煎一筋だった父親と衝突した。
「味で揉めて喧嘩しました。私は営業出身なので、お客さんが美味しいと思うコーヒーを作りたかった。『コロンビアがいい』って言われたらコロンビアを使ったブレンドを作るとか、お客さんの要望に応えなあかんと思ってた。一方父親は、自分が美味しいと思う焙煎にこだわった。『じゃあお前がやれよ』と言われて翌日から父親は一切店に関わらなくなりました」

コーヒーへのこだわりが生んだ「成長し合う関係」
自分の意思や好みを通すよりも、客に喜んでもらうことが大切だった古家にとって、コーヒーだけは特別だった。営業マン時代から、マスターたちにも「コーヒーを大事にしてくれ」と口を酸っぱくして言っていた。
「コーヒーをないがしろにして商売なんか成り立たへん、と思っていたからです。でもさすがに、豆屋がコーヒーの淹れ方にまで口を出すことはできない。だからしょっちゅう店に足を運んで、おいしいコーヒーの淹れ方を実演し、同じようにやってほしいと頼んでいたけど、絶対守らないんですよ。それがジレンマだったね」

どうすれば彼らの役に立てるのか。考えた末に行き着いたのは、思い描いていたスタイルを自分の店で実践することだった。
「こうすればしっかりお客さんが来るよ、という例を作りたかったんです。モデルショップみたいなつもりでした。営業マン時代、コーヒーに手を抜かない店にはお客さんがついていると実感していたので、それを実証したいと。だから自分の店の売り上げや収支もオープンにしました」

コーヒーの存在をさらに特別なものにしたのは、スペシャルティとの出会いだった。2000年頃のことだ。
雑味のないその味を体感した。より美味しいコーヒーを客にも飲んでほしい、純粋にそう思った。だからといって、大幅に味を変えたり、価格を上げたりすると顧客が離れていく怖れもある。利益が圧迫されることには目をつぶり、スペシャルティのコーヒー豆を使い続けた。

「自分自身が一番悩みましたよ。雑味がない分、味が軽くなってしまうので、焙煎の方向性がおかしいんちゃうかと思ったりね。だから味を重たくできるよう試行錯誤しました」
急に味が変わらないように焙煎を調整したものの、「味が薄くなった」というクレームが来ることもあった。だが、古家は意志を曲げなかった。
「色々と飲み比べてやっぱり美味しいと思っていたから。納得してもらえるように繰り返し説明しながらも、お客さんの要望に沿って味を微調整していくうちに、『まあ任せるわ』と言ってくれるようになったんです」
それまでに築いてきた関係が強固なものだったからだろう。取引が途絶えることはなかった。その時に初めて、顧客の要望に応えるだけでなく、一緒に成長していくことがより大きなやりがいにつながると気づいた。今は、客の好みや理解度に合ったコーヒーを提案している。

考えが変わっていく中で、かつては理解できなかった父の想いも分かるようになった。2002年の焙煎・ケーキ工房のオープンに合わせて販売を始めた「グランファザーズ ブレンド」は、父に「俺のコーヒーを美味しいと思わせたろ」という気持ちで作ったコーヒーだ。
それでも、商売人でありたいという根本的な姿勢は変わらない。
「お客さんを裏切らない美味しいコーヒーを作ろうというのが一番ですね。やっぱりお客さんが好きなので自分のこだわりを押し付ける商売には自信がない。自分ができることでお客さんに満足してもらう、それが自分には合っているんだと思います」


スタッフの成長が経営の醍醐味
いわゆる徹底した顧客目線を貫いてきたおかげか、30年間の経営の中で、古家は大きな壁にぶつかったことがないという。唯一とも言える悩みの種が人材だった。3号店を出した2012年まではアルバイトのスタッフが多く、定着率が低い状況で店を回さなければならなかった。
本気で店に関わってくれる人と一緒に働きたいという思いから、社員を積極的に採用するようになった。現在では30名弱のスタッフの約1/3が社員だ。勤続10年ほどになる社員も3名いる。

経営理念に「コーヒービジネスで輝く人を創出する」とある通り、自分の店を持つスタッフを増やすことが古家の目指すところだ。実際、今までに8名のスタッフが独立を果たした。客として店に通ううち、「開業したいと思う気持ちに火がついた。一回飲食業を離れたけれど、この店に来てやっぱりやりたいと思った」と入社したスタッフもいる。
「叶うなら社員全員に店を持たせてあげたい。自分で店をやる楽しさを知ってほしい。苦労しながらどうにかして売り上げを上げて、理想の店を作ってもらうのが私の夢です」
だからこそ、コーヒーの淹れ方などを細かく指導することはあまりない。それぞれの自主性に任せている部分が大きいため、自分の技術や接客に自信をなくすスタッフも多いという。
「自分で試したことがうまくいったのか、お客さんの反応を見て学ぶことが成長につながる。自信をなくしているスタッフには、『コーヒーをたくさん飲みなさい』『よその店も見なさい』と声をかけます」

苦しい時期を経てスタッフの顔つきが変わったとき。それが古家にとって、一番のやりがいを感じる瞬間だ。独立を志すスタッフにはこんなアドバイスを送る。
「しっかり儲けるという気持ちを持たないとダメよって。じゃないと私が見てきた喫茶店のように衰退していってしまう。10年後にリニューアルするのか、2号店を出すのか、何かしら新たな展開を生み出せるように儲けることが大事だよと伝えています」
以前は儲けることなど頭になかった古家の心境が変化したのは、スタッフを一人前にしなければ、という自覚が芽生えたからだ。
「みんなが愛情を持って店のために働いてくれるのを見て、やっぱり自分も老体に鞭打って頑張らなあかんなって。しんどいけれど、年々喫茶店をやる楽しみが大きくなっているのは、その姿勢に刺激されているからじゃないかな」
かつては考えもしなかったカフェの経営者になり30年。その間に得てきた「感謝される喜び」は今、次の世代を育てるエネルギーとなり、古家を突き動かしている。
文:KANA ISHIYAMA
編集:中道 達也
写真:Misa Shinshi

MY FAVORITE COFFEE人生を豊かにする「私の一杯」
お客さんの感想も踏まえて焙煎したコーヒーが、自分のイメージ通りだった時。お客さんが美味しいと思うコーヒーを自分も美味しいと感じられる時に幸せを感じます。

このロースターのコーヒー豆を購入する








