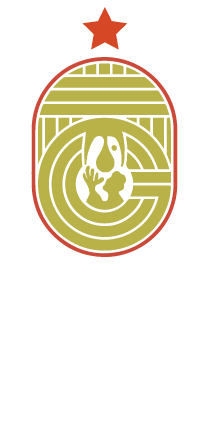


「MORE THAN JUST A COFFEE 1杯のコーヒーにとどまらない体験を」というスローガンを掲げ、主に10件ほどのコーヒー生産者とのダイレクトトレードを行っているカリオモンズコーヒーロースター。2009年、ケータリングカーから出発し、現在は“すでにある”空間に新しい生命を吹き込んだ2店舗を長崎県内に構えている。コーヒーを通して生き方を見つめ続ける創業者・伊藤寛之さんの物語りとは。 ※文中敬称略

世に出ていない、まっさらな存在
コーヒー店やカフェに限らず、店や会社の屋号には創業者の思いや個性、価値観、哲学が宿るものだ。2009年に産声をあげた「カリオモンズコーヒーロースター」もその例に漏れず、創業者である伊藤のオリジナリティが映し出されている。
「カリオモンは、エチオピアの言葉で『コーヒーセレモニー』を意味しています。エチオピアの文化的、伝統的な習慣であり、今では行事や儀式のように捉えられていますが、そもそもは日常に連なっているひとときというか、狩猟民族が狩りから帰って来た後にお茶をする時間や空間を表す言葉として使われていたようです。
僕が惹かれるのは、『カリオモン』という言葉のふわっとして言語化しきれないところ。言葉にはとても長い歴史があるのに的確な表現が見つからないことが、未知の世界に触れているようでワクワクする。だから、店の意味を訊かれたときが一番困るんです(笑)。
そこに『ズ』をつけたのは、語呂がよかったのと、当時『カリオモンズ』でネット検索したら1件も引っかからなかったから。自分の店の名前がまったく世に出ていないまっさらな言葉だと思うと、胸が高鳴りました」

スペシャルティコーヒーという「未知の世界」
長崎市内のカフェでアルバイトをしていた19歳の伊藤をコーヒーの世界にぐっと引き込んだのは、福岡市内にあるスペシャルティコーヒー専門店だ。そこで飲んだケニアが、まさに“未知との遭遇”だったという。
「まずコーヒーの色が黒というよりも透き通った赤に近くて、味も自分が知っているコーヒーとはまったく違うからおいしいとも感じない。そのことに衝撃を受けて長崎に帰ってきたんです」
以来、時間を見つけては「スペシャルティコーヒー」というキーワードをネット検索し、引っかかった記事や店の情報を一つも取りこぼさない勢いで頭に叩き込んでいった。

「2000年代半ばは、日本ではまだサードウェーブの認知度が低く、スペシャルティコーヒーに関する情報も乏しかった頃。カップ・オブ・エクセレンス(Cup of Excellence)にも84点で入賞できたりと、今ほど当たり前においしいコーヒーを飲める時代ではなかったんです」
そんななかでもアンテナを研ぎ澄ませていた伊藤は、スペシャルティコーヒーを販売している全国の数少ない店から焙煎豆を取り寄せ、自分で淹れて飲むことを繰り返していた。その後、焙煎も始めた伊藤は、2009年、23歳のときにカリオモンズコーヒーを創業した。

「知人から15万円で売ってもらった中古のケータリングカーと15万円の小さな焙煎機で店を始めたのは、仕事という名目でいろんな種類のスペシャルティコーヒーを飲みたかったからです。と同時に、僕の世界を大きく広げてくれたスペシャルティコーヒーの魅力を言葉で説明するだけでは伝わらない、伝えるためには『飲む』という体験を共有するしかないという思いもありましたね」

伊藤が調べた限り、当時の長崎には実店舗でスペシャルティコーヒーを飲めるところはほとんどなかったという。
「何もないところから道を切り拓いていく方が性に合っているので、ひとつもないのであればそこにトライする価値は十分にあるのかなと。 だから『コーヒーは苦手だけど、おいしいと言われて来ました』というお客さんのように、コーヒーの入り口として選んでもらったときは、僕らの腕の見せどころであり、勝負どころだと思っています。
というのも、もしそこで失敗したら、その人の中でコーヒーという選択肢は永遠に失われてしまうかもしれないからです。それはコーヒー業界全体にとって大きな損失。未知の世界を案内し、ひとりのコーヒーラバーを生み出す重要な役割を担っているんだと思うと、おのずと身体が熱を帯びてくるんです」


「人」が見える方が心地よい
生産者とのダイレクトトレードを行うカリオモンズコーヒーが掲げる「サプライチェーンにおいて不幸な人をつくらない」というモットーは、創業2年目、2011年からコーヒーの生産地に通い始めた経験をもとに生まれたものだ。
「世界的にスペシャルティコーヒーシーンが盛り上がっていくなかで、消費国からいろんな(コーヒー豆の個性や品質、生産管理など)要求を突きつけられることに疲弊し、翻弄されている。生産者の方々に直接会ってそんな苦労話を何度も聞くうちに、自分たちが日々楽しんでいるスペシャルティコーヒーが生産者の幸せにつながっているのか、疑問に感じるようになったんです。実際、コーヒー農家を辞めてしまった友人もいますしね」

コーヒー屋といえども、コーヒーを売るだけが仕事ではない。そんな伊藤の感性は、「MORE THAN JUST A COFFEE 1杯のコーヒーにとどまらない体験を」というスローガンにも表れている。
「たかだか10gの豆からできた150cc程度の飲みものだけど、それができるまでにはたくさんの人の手が加わっていて、その1杯で飲んだ人の一日の調子やパフォーマンスを左右するほどの力も持っている。そういう飲みものだということを自分たちが自覚しておくために、スローガンを掲げています。
店のバリスタやロースターだけでなく、世話になっている生産者さんも、お客さんにコーヒーを届けるためのチームだと僕は思っています。だから、海の向こうで起こっていることも自分たちのこと。その感覚がなければ、お客さんにも一杯のコーヒーに込められたものを伝えきれないと思っています」

ケータリングカーから船出したカリオモンズコーヒーには、3年半ほど営業した大村店(2号店)を閉店し、長崎市内に移転したという歴史もある。
「自分たちが働くだけの場所になっていたことが、一番大きな理由です。朝、店を開ける前に別のまちからやってきて、夜、店を閉めたら別のまちへと帰っていく。だから、大村で暮らしている人たちがどういった生活を送り、どういったサイクルで1年を過ごし、人々の間には日々どういった噂が流れているのか……といった営みが見えてこない。
大村の人たちからは温かく迎えてもらっていたけれど、それに対して僕らがお返しできている感覚が薄く、一方的に与えてもらっているような関係性があまり心地よくなかったんです。
その点、長崎市に移転してからは、店の外でお客さんと会う機会が格段に増えたので、まちの人たちの人間模様がわかりやすくなりました。たとえば、店では全然会話をしなかったお客さんと飲み屋でばったり会って話が弾んだりと、ひとりの人間どうしとして触れ合う機会を持てることが僕はうれしい。店のカウンターの中にいると、どうしても仕事モードになってしまいますから」


すでにあるものに価値を見出す
かつては石材加工場として使われていた空間に新しい生命を吹き込んだ時津店では、衝立や椅子、ドラム缶など、客たちが持ち寄ったものも店の一部となっている。築40年以上のビルの1階にある長崎店も、家具屋と喫茶店が共存していた空間を部分的にリノベーションする際、もとからあるものは極力そのまま残したという。
「僕たちはコーヒー豆を生産者さんから買い付けるところから始まるストーリーをお客さんに伝えているので、歴史や物語を内包した古い建物やモノとも調和していると受け取ってもらえているのだと思います。
僕自身、すでにあるものに価値を見出す方が好きなのか、得意なのかはわかりませんが、洋服にせよ、車にせよ、新品よりも中古品の方が好きなので、欲しいものがあればまず中古で手に入るかどうかを調べます。これだけモノがあふれている時代において、中古品を使う方が合理的だしムダもない。仕事道具も普段の生活で使うモノも、中古の方が早くなじんで、自分の手足の延長線上になってくれる気がしますしね」

そんな伊藤の考え方は、2020年から始めた「ナイスパス」プロジェクトにも表れている。アパレルブランドや地元の大学と連携した同プロジェクトは、各家庭でたまりがちな紙袋を店頭で回収し、再利用するという取り組みだ。
「店としては新品の紙袋を仕入れなくて済むので、経費削減にもなります。エコなイメージとは裏腹に、実はプラスチック製の買い物袋(レジ袋)の4倍ほどCO2を排出している紙袋を再利用することで、環境にも貢献できますしね」
プロジェクト開始後は、カステラ屋やスターバックス、今はなきJ-PHONEなど、さまざまな企業や店舗の紙袋が店に集まってくるようになった。
「お客さんとしても、捨てる罪悪感もないですし、掘り出し物を見つけられるかもしれない、というゲーム的な要素を楽しめると思います。『店が中古の紙袋を使うのは失礼、ましてや違う企業や店の紙袋を使うなんて論外』という“常識”を塗り替え、そういう取り組みが店のブランド力を高めるような社会をつくっていきたいですね」
伊藤らが呼びかけを始めてから約2ヶ月経った今、このプロジェクトに参加する全国の企業や団体、教育機関は100を超えているという。

日常の中にも未知はある
老後は地元である雲仙市に帰り、田舎暮らしをしたいという伊藤は、とあるメディアに寄稿したエッセイの冒頭でこう書いている。
“旅とは知らない場所へ行くことではない。また、遠くへ行くことでもないだろう。日々の中に溶け込む未知を体験することもまた、ひとつの旅と言えるのではないだろうか。”
「新しいものを求め続けると、幸せに向かっていく感覚が薄れるだけでなく、人間のサイズ感を超えてしまう気がします。 極論すれば、うまい飯と水と空気さえあれば十分じゃないか、という感覚を僕は持っていたいんです。社会が目まぐるしく変化している時代だからこそ、心地よさを失わないためには、欲をコントロールしなければいけないのかなと思っています」
だが、伊藤は決してやせ我慢をしているわけではない。
「世の中にまったく新しいものはほとんどなくて、大半がリバイバルだと僕は思っています。だから『未知=まったく新しい』ではなく、日常の中にある昔に帰っても、十分、未知の世界を堪能できるのかなと。たとえば、昔はどこの家にもあったような棚の取っ手ひとつとっても、当時を知らない僕らには新しい発見として捉えられますから」

2021年8月、カリオモンズコーヒーは創業13年目を迎えた。サードウェーブの後押しもあり、長崎という地方都市でもスペシャルティコーヒーが浸透し、未知の存在ではなくなった今、伊藤は何を思うのか。
「おいしいコーヒーを当たり前に飲めるようになったのはとても喜ばしいことですが、その反面、スペシャルティコーヒーが特別なものではなくなり、悪い意味でコモディティ化していく危うさもあると感じています。
以前のスペシャルティコーヒーは、天候と栽培方法と品質管理の三拍子揃わなければ生まれ得ない“選ばれし存在”でした。でも今は、技術が進歩し、ノウハウが蓄積されてきたおかげで、人為的においしいコーヒーを作りやすくなっています。
とはいえ、生産者の労力が軽減されているわけではないので、おいしいで終わらせちゃダメだし、その価値を正しく伝える活動は続けていきたいなと。『コーヒーの2050年問題』としても取り上げられているように、将来的においしいコーヒーの生産量が大幅に減る可能性が高いことはわかっているわけですから」

社会に定着して久しい「顔が見える関係」という言葉が生まれたのは、昔は当たり前だったその関係が経済発展とともに失われてしまったからだろう。これまで10数年の間、カリオモンズコーヒーが1杯のコーヒーを通して伝え続けてきたのは、つまるところ「幸せは、遠くに行かなければ手に入らないものじゃない」というメッセージなのかもしれない。
文:中道 達也
写真:Kenichi Aikawa
MY FAVORITE COFFEE人生を豊かにする「私の一杯」
人に淹れてもらったコーヒーです。どこかの店で飲む一杯にせよ、店で仕事をしているときにスタッフが気遣って淹れてくれる一杯にせよ、評価せずに楽しめるところが魅力です。

このロースターのコーヒー豆を購入する








