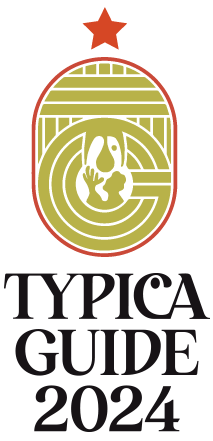


渋谷駅から私鉄を乗り継いで30分弱。世田谷区の西に位置する喜多見は、川向こうに高級住宅街として知られる成城を臨みながらも、自然や人情味を残すエリアだ。少し脇道に入れば野菜の無人販売所があるのどかなこの街に、オーダー焙煎にこだわり続ける老舗焙煎所がある。休日ともなると焙煎2~3時間待ちは当たり前のビーンズ喜多見(1988年創業)だ。
現在、店を運営するのは清水則江さん・さゆりさん姉妹と、「アニキ」こと宮下信人さんの3人。オーダー焙煎に魅せられて働き始め、この店独自のスタイルを守り続ける彼らの信念とは。(文中敬称略)

開かれた専門店
喜多見駅前には、100店以上が軒を連ねる商店街が1kmにわたって続いている。大型スーパーやチェーン店、昔ながらの個人商店が入り混じる、人々の生活の拠り所だ。その一角に、「自家焙煎珈琲豆屋」の看板を掲げるビーンズ喜多見(以下、ビーンズ)はある。
日本でも数少ないオーダー焙煎のコーヒー豆専門店だが、頑固な老舗の雰囲気は一切感じられない。木の温もりを感じるレトロな店の扉を開けた先に待ち受けるのは、所狭しと並ぶコーヒーの生豆。「うちの店にお嫁に来て欲しい豆が多すぎて、溢れかえっちゃうんですよね。最近は自制しています」と則江は言う。

ビーンズの豆はパワフルな香りと、奥行きのある味わいが特徴だ。直火の小型焙煎機で焙煎したてのコーヒー豆を提供するからこその産物なのだ。
「焙煎した豆を持って電車に乗ると、『香ばしい香りがする』と周囲に気づかれるほど香りが強いんです。家族も友人も、うちの豆でコーヒーを淹れたとき、部屋中に広がる香りに驚きますね」(宮下)
ビーンズで扱うコーヒー豆は40〜50種類。あらゆるニーズに対応できるよう、多様な産地や味、香りのものを満遍なく揃えている。そして、8段階以上ある焙煎度合いから、客の好みに合わせて注文後に焙煎するのがビーンズのスタイルだ。
「コーヒーは嗜好品なので、お客様の好きな焙煎、好きな挽き方、好きな抽出器具で楽しんでいただきたい。その間口を広げて、旅行するように自分の好みを探究できるのがオーダー焙煎ならではの楽しみ方ですね。実際、このスタイルに魅了されて1つの銘柄ですべての焙煎度合いを制覇するお客様もいますから」(さゆり)

生豆の選択肢が多い分、接客には焙煎の知識に加えて、相手の好みを細かくヒアリングして提案する力も求められる。ビーンズでは仕事を分業せず、産地への理解が深い3人が接客から焙煎までマルチにこなしている。ゆえにどのタイミングで店を訪れても、客はコーヒーについて誰かに相談できるのだ。
「例えばナッツテイストと一口に言っても、アーモンドなのか、ヘーゼルナッツなのか、ピスタチオなのかというレベルまで聞き出すことで、どの豆をどの焙煎度合いにするか提案できるようになるんです」(則江)
こうして積み重ねてきた経験と信頼が、ビーンズの礎になっている。注文の約9割をリピーターが占めており、創業当時から通う人や、こっそりストップウォッチで焙煎時間を計測するコアなコーヒー愛好家もいるという。

その一方で、近所の子どもがはじめてのおつかいデビューをビーンズで経験するなど、“街のコーヒー屋さん”の一面も持っている。店の顔となっているのは、最年長宮下。流暢な英語でウィットに富んだジョークを飛ばす、愛されキャラだ。則江・さゆり姉妹も「世話焼きな近所のアネさん」感覚で、フラッと立ち寄った客を引き込んでいく。
「おばあちゃんが八百屋でキャベツを買ったり、豆腐屋で豆腐を買ったりする感覚で利用できる店なんです。味では他に負けないこだわりを持っているのに、カッコつけない。そこが魅力です」(宮下)


感動の裏にある地道な積み重ね
オーダー焙煎は、創業者である先代のマスターから受け継ぐ、ビーンズの伝統だ。最古参の則江も、他とは違うスタイルに魅せられた来店客の一人だった。出会いは、大学生になった2002年。地元の長野を離れて上京後、一緒に暮らしていた姉に紹介されたのがビーンズだった。
「注文してから自分のために焙煎してくれることに感動したんです。私もその技術を学んで、自分が感じた高揚感をお客さんに提供する側に回りたかった。今もその時の思いは忘れませんね」
初来店の翌月、則江は研修生募集の張り紙を見て我こそはと意気込んだ。着古したTシャツとジーパンに金髪。その姿を見たマスターから「学生さんは雇ってないよ」と門前払いされそうになったが、「頑張りますのでお願いします」と食い下がり、週1で通う研修生になった。

どうせ続かないだろうと見くびられながらも、ひたすらハンドピックを続けた則江は、次々と辞めていくアルバイトスタッフの穴を埋める存在となった。彼女が“地味”な仕事を投げ出さなかったのはなぜだろうか?
「料理屋で皿洗いや掃除をやるのと同じだと受け止めていたので、特に不満を感じることもなかったですね。もっと効率的にできないかなどと自問自答しながらハンドピックをしていたのですが、じっくり時間をかけた作業が商品の価値として、お客さんの喜びや癒やしにつながっていると実感できたからだと思います」

大学卒業までビーンズで働き続けた則江は、一般企業に就職したものの、古巣に帰ってくることになる。
「社会の洗礼を受けて心身の調子を崩した時に、マスターが『戻ってきたら?』と声をかけてくれたんです。それを機にビーンズで働き始めたら、お客さんたちから『おかえりなさい』と言ってもらえた。私の居場所はここなんだな、と心が定まりました」

“自分の給料は自分で稼ぐ”のがビーンズのスタンスである。社員となった則江は、ネット販売を始めたり、イベントに出店したりと、ビーンズで自分の居場所を作るために奔走する。その時に「ちょうどいい相方」として上京してきたのが大学生になった5歳下のさゆりだ。
「当時興味があったのは、親に内緒で取った二輪免許でバイクに乗ることくらい。でも、姉を手伝っていた学生時代のうちにはもう、焙煎の奥深さに魅了されていたんです。たった3秒、ドラムを引き上げるタイミングが遅れただけで焦げた印象の味わいになったり、味わいに厚みが出なかったり。設計されたプロファイル通りに焙煎しても、到達できない世界があることを知りました。その悔しさは、いつの間にか探求心に変わり、コーヒーの世界にのめり込むきっかけになったんです」(さゆり)

焙煎したい思いとは裏腹に、ひたすらハンドピックや計量、袋詰めなどの作業に明け暮れる時代もあった。本格的に焙煎に携わるまで5年かかったが、「その地道な下積み経験や悔しさも糧になっている」とさゆりは言う。
「ビーンズは少量焙煎を売りにしているので、一日の焙煎回数が100回を超える日も多いんです。そのすべてに神経を使って焙煎と向き合ってきたので、コーヒー豆の香りが開く瞬間が自然と見極められるようになりました。努力で得た職人技です」
たゆまぬ研鑽があってこそ、アットホームな雰囲気が魅力で長年人々に愛されてきた今のビーンズがある。過去には、憧れを抱いて働き始めるも、地味な仕事が続く下積みに耐えきれず、店を去った人も少なくない。


継承と発展
家具の貿易会社と不動産業を営む家で育った則江とさゆりは、幼少期から『商人の子は商人であるべき』という家訓を言い聞かされて育った。さゆりも一度は就職したものの、会社員には向かないと悟ってビーンズに戻ってきた。人から指示されて動くより、自分で一から考えて行動する方が性に合うのだ。
さゆりが働き始めた頃、則江に「ビーンズでコーヒーの勉強をしたい」と連絡をしてきたのが、宮下だ。会社勤めをしながら、週末になると、コーヒーに身を捧げる生活が3年以上続いた。

「今まで飲んできたコーヒーの中でも格段に香りが強く、そのうち自分でも焙煎してみたいという気持ちが芽生えてきたんです。『正社員では雇えない』と言われましたが、週末だけでもコーヒーについて学べるありがたさで頭がいっぱいでしたね。一度きりの人生ですし、自分のやりたいことをしたいなと。人生の決断ポイントの1つだったと思います」
その後、宮下は突如として会社を辞め、ビーンズへの転職を独断する。一回り以上年下の姉妹から「風邪で休んでも給料が入ってくる手厚い大企業のようにはいかないよ。自分の給料は自分で稼いでね」とビーンズスタイルの洗礼を受けても怯むことはなかった。当時運営していたカフェのモーニングを新たに企画し、姉妹の協力のもとで実現に漕ぎ着けた。

当時、則江31歳、さゆり26歳。父から『30歳までに東京で花開かなければ、実家に帰ってこい』と言われていた中で覚悟を決めた。事業をするなら親からの援助は受けないと心に決めていたため、2階を改装してカフェを開く時もできる限りDIYで済ませた。3人ともが同じ味を出せるよう細かくプロファイルをまとめたりと、ビーンズらしさを残しながら発展させる方法を模索していった。そして、3人体制で2014年に会社を設立。「ビーンズ喜多見」の看板はそのままに先代マスターから事業を受け継いだ。
一度目の転換期を迎えたのは2018~19年。則江とさゆりの妊娠、出産だ。店の経営と母親業を同じ比重で両立させるために、カフェを休止して焙煎一本に絞ることを決めたのだ。
二度目の転換期を迎えたのは2020年。同業者とのつながりを作って世界を広げていく中で、ビーンズにはない魅力を持つ、低温焙煎と出会ったのである。

「繊細な香りや味わい、甘さを持つ低温焙煎の技術を取り入れたら世界が広がる、と確信しました。ただ、実際に技術を習得しても、低温焙煎ならではの繊細な香りは出せた一方で、ビーンズらしい力強い香りを出すのが難しかったんです」(則江)
「力強い香りは、少量で直火焙煎するからこそ生まれるもの。それに慣れ親しんだお客さんからは『美味しいけど、いつもの方がいい』と言われてしまった。うまく融合させるために、ビーンズらしい味わい作りをすべての生豆で見直しました」(さゆり)
生豆の中には、それまで通りの焙煎方法を活かした方が良いものもあれば、低温焙煎を取り入れた方が良いものもあった。例えば、力強く、華やかな香りはあるものの、後味の雑味がネックになっていたモカは、香りの魅力を最大限引き出した上で、後味もクリアになった。豆に与える負荷を最小限に抑えられる低温焙煎によって、香りの寿命が延びたのだ。「新たな手法を手に入れることができましたね」と則江は言う。

味覚も似ており、絶妙なコンビネーションを見せる3人。車でいえば、企画力や行動力に長けたさゆりはエンジン、縁の下の力持ちとなって、ひたすら走り続ける宮下はタイヤ、バランスを取りながら舵を切る則江はハンドルだ。店を拡大すべく、スタッフの増員を考えたこともあるが、クオリティを維持するには3人のままが良いという結論に至った。ゆくゆくは次世代のビーンズを担う人材を探していきたいという。
「何十年も一緒にいて、同じモチベーションで一つの目標に向かっていける貴重な存在ですね。みんな自己主張が強いので口論になることもありますが、おしくらまんじゅうのように同等の力でぶつかり合えるからこそ倒れずに立っていられる。誰が欠けてもダメなんです。本音で話せる環境があり、日々笑い合える仲間がいるのは幸せなことです」(則江)

効率よりも大切なこと
ビーンズを支え続ける存在は、3人だけではない。オーダー焙煎に応えるオリジナルの小型焙煎機もまた、ビーンズとは切っても切れない関係にある。一度に焙煎できる生豆は最大600gと、大型焙煎機の数十分の一。サンプル用にも見られかねない焙煎機だ。
「名の知れたロースターで焙煎されたコーヒーを飲み比べる日を、定期的に設けているのですが、うちの小型焙煎機ならではの香味を発見できることがすごく多いんです。大量にまとめて焙煎すると、引き出せない香味があるのだと感じますね」(さゆり)
一方で、焙煎機が小さく保温力が低いために、エアコンの風や扉を開けた時の外気などの外的要因に左右されやすいという、じゃじゃ馬な一面もある。投入する温度や焙煎する豆の量に合わせた火加減は、シビアなコントロールが求められる。そして何より、ワンオーダーごとの焙煎は、効率とはトレードオフの関係にある。

「1回の注文で焙煎機を10分占有しますし、豆の種類や焙煎度合いのバリエーションが増えるほど焙煎の回数も増えます。1日中焙煎に追われるような毎日ですが、このスタイルは譲れないですね。お客さんも自分だけのために焙煎してもらえることに価値を見出してくれているので、時間をかけてでも期待に応えたい。小型焙煎機でお客さんの顔を思い浮かべながら焙煎するのは、家族のために料理をする感覚に近いですよね」(さゆり)

3人が手間ひまをかけているのは焙煎だけではない。小型焙煎機に最適な産地の選定や、コーヒーキュレーターとの交渉、サンプルの取り寄せに始まり、カッピング、焙煎、ハンドピック、デザイン、接客、販売まで、全て自分たちでプロデュースしているのだ。
「お客さんに喜んでもらえるコーヒー豆に仕立てるためにどんな服を着せてあげようか、どんな香りや味わいを作ってあげようかと、娘や息子に愛情を注ぐ感覚をみんなで共有しているんです」(則江)

守り続けるという挑戦
これまで自分のやりたいことに食らいつきながら突き進んできた3人。現在も宮下はビーンズ後援のもとで、自身のプライベートブランド『旅雲珈琲』を立ち上げてイベントに出店するなど、還暦手前でもなおチャレンジを続けている。コーヒーに対する情熱は、何年経っても尽きることはない。
「今の目標は、新型の焙煎機の開発です。味わいは変えずに1kgか2kgまで対応できるようにして、外的要因に左右されやすい小型焙煎機のデメリットを克服したいんです。卸の注文も増えてきているので、新型を何台か導入して、焙煎スペースも広げたいですね」(則江)

進化を続ける3人だが、胸に抱くのは「ビーンズらしさ」を守っていくという変わらぬ信念だ。
「低温焙煎を始めた頃、常連さんにサンプルを渡したら『そんなことしなくていいんです。ビーンズの味を信頼しているので、僕に味の評価を求めないでください』と言われた時は涙が出そうなくらい嬉しかったですね」(さゆり)
オーダー焙煎で一人ひとりと向き合う中で築いた関係には、店員と客の間柄を超えた温かさがある。
「創業当時から通うお客さんに『自分の棺桶にはビーンズの豆を入れるよ』と言われたのが衝撃でした。冗談を言う方ではないので、本気でうちのコーヒーを愛してくれているんだ、と感動しましたね」(宮下)
ビーンズのありようは、非効率の中にこそ豊かさがあることを教えてくれる。かけがえのない3人が一途に守り続ける、かけがえのない店には、この先もパワフルな香りと笑い声が広がっているに違いない。
文:軽部 三重子
編集:中道 達也
写真:Kenichi Aikawa

MY FAVORITE COFFEE人生を豊かにする「私の一杯」
何度もオリジナルブレンドを試作する中で、理想を超えた一杯を生み出せた時ですね。新たな発見への感動と、無限にあるコーヒーの組み合わせの中から、綺麗にピースがはまったような達成感を感じます。そんな時は早くお客さんに伝えたい思いで胸が膨らみます。(則江・さゆり)
仲間とツーリング用の自転車で山に登った時に、山頂で淹れたモカは過去最高の一杯でしたね。真夏で喉がカラカラなのに、熱くて苦いモカがなぜかすごく美味しくて、忘れられない味になっています。(宮下)

このロースターのコーヒー豆を購入する








