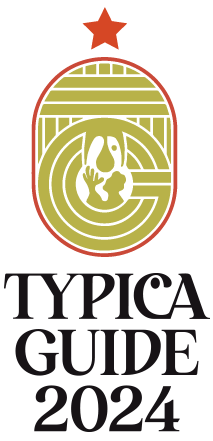


コロナ禍の2020年7月、大阪・船場のオフィス街の一角にオープンした「aoma coffee」。店内の座席は少なく、極めてコーヒースタンドに近い形態だ。「焙煎においては『整える』ことを重視している」という店主の青野啓資さんに話をうかがった。 ※ 文中敬称略

バランスのとれた店づくりを
「かしこまった接客があんまり好きじゃないんです。僕はうどん好きなので香川のうどん店によく行くのですが、『次、兄ちゃん何する?』というようなおばちゃんたちのフランクな接客が好きなんですよね」
極めてコーヒースタンドに近いスタイルの「aoma coffee」には、そう語る青野の考え方が反映されている。開店当初は4席ほど設けていたが、「よりラフな感じにしたい」との思いで簡素な椅子を置くだけにした。近くにある有名な立ち食いうどん屋で食事をした後に立ち寄る客も多いのだという。

夏ならばTシャツに短パンなど、ゆるい服装で店に立つ青野の原点には、カフェ文化が発達しているオーストラリアのメルボルンで目にした光景がある。
「カフェで出されるコーヒーのクオリティが高く、コーヒーを飲むためだけにカフェに行く人たちもいる。好きなバリスタに自分の好みを注文し、2杯、3杯とおかわりもする。何よりお客さんとスタッフが対等な関係で、さくっと気持ちよく接客しているのが印象的でした」

そんな青野が焙煎において重視しているのは「整える」ことだ。
「豆(素材)の個性を活かしながら他の要素を整えてバランスを取ることを心がけています。スペシャルティコーヒーを出すロースターはよく『豆の個性をいかに引き出すかを心がけている』と言いますが、僕は豆の個性を出しすぎないことも大切だと思っています。
というのも、個性が強い豆の個性を活かすと、ファーストインパクトはよくても、カップ1杯飲むのはしんどいコーヒーになってしまいかねません。そういう豆でも飲みやすく仕上げるのもコーヒー屋の仕事かなと。だから、豆の個性を引き出すというよりは背中をぽんと押す感じです。『整える』というのは、豆だけに向き合うのではなく、全体的なバランスを取るという意味ですね」

「浅煎り」に魅せられて
現在、44歳の青野がコーヒーの世界に足を踏み入れたのは30歳のとき。それまで飲食店で働いた経験はなかったが、将来はカフェをやりたいと思い描きながら、カフェ事業部のある飲食系の会社に転職した。
「でも、コーヒーが好きだったわけではないんです。むしろ紅茶派で、みんな苦いコーヒーを我慢して飲んでいるんだと思っていたくらいです。配属されたカフェで出しているエスプレッソを飲んでも、薬みたいでおいしいとは思えませんでしたから」

京都のカフェやコーヒー店を巡っていた青野は、自家焙煎したスペシャルティコーヒーを出す店でこれまでの常識を覆すコーヒーと出会う。
「すっきりしていてフレッシュで酸味がある。最初はおいしいと思わなかったけれど、それまで飲んできた苦いコーヒーとはまったく違う味に興味が湧いたんです。それが浅煎りだと知ったのはしばらく経ってから。飲み続けるうちに口がどんどん慣れて、おいしいと思えるようになっていきました」
いつしかコーヒーの世界にのめり込んでいた青野が、コーヒーの専門店で働きたい、焙煎をやってみたいと思うのは自然な流れだった。その後、大阪で複数のカフェを展開するELMERS GREENに転職。新たに自家焙煎を始めた店舗の浅煎りコーヒー担当として、豆を焙煎する日々が始まった。

「浅煎り」の可能性を確信していた青野は、2、3年目頃から会社に「大阪市内で浅煎りに特化したコーヒー屋を出しましょう」と直訴するようになった。
しかし、ブルーボトルコーヒーが上陸する前で、サードウェーブと呼ばれるコーヒーブームもまだ訪れていない時分である。会社は「そんな店、お客さん来ないよ」と青野の提案を受け入れなかった。ようやくゴーサインが出て浅煎りに特化した店(EMBANKMENT Coffee)をオープンできたのは5年目となる2017年10月のことだった。
「そこに至るまでは、まわりのスタッフとしょっちゅう衝突していましたね。クラシックなコーヒーを好む人たちが集まる社内で『浅煎り』を推しているのは僕だけ。自身、味方がいない状況に燃えてしまうタイプなので、意固地になっていましたし、まわりに迷惑をかけていたと思います。今は丸くなったというか、自分で深煎りをやろうとは思わないけれど、これもひとつのコーヒーだと受け入れられるようになりました」


コーヒーが運んできた新たな人生
青野の前職は、染め物職人だ。デザイン系の大学を卒業後、手に職をつけたいと京都の染物屋に就職。染工場で1日じゅう誰とも話さず、黙々と作業をやる日々を過ごしていたという。
「当時は目指すものが何もなく、機械のように淡々と仕事していました。作業に没頭していたら無になれるのが心地よかったですし、それで給料をもらって、好きなものを食べたり、買ったりできれば満足だったんです」
しかし、30歳に近づくにつれ、自分の人生はこのままでいいのか、という疑問が湧いてきた。30代からは別の人生を生きたいという思いが、青野をコーヒーと引き合わせた。
「コーヒーを仕事にしてからは、食べものについて考えながら食べるようになったり、おいしいかどうかの線引きが明確になったり……。コーヒーの味を意識するようになったことで、食が楽しいと思えるようになりました。
人との接し方も変わったところのひとつです。自分ひとりで何かに集中するのも好きだけど、人に囲まれている方が好きだとわかったんです。実際、大阪だけでなく、東京や福岡など、同業者の友達がたくさんできましたから」


対等な関係を求めて
2019年、コロンビアのコーヒーの生産地を10日ほど訪れた経験は、青野の胸に刻まれているという。現地の人々と触れ合うなかで、『生きていくために大変な思いをしながらコーヒーを作っている貧しい国の人々』という思い込みはすっかり覆されたのだ。
「生産者の人もエクスポーター(輸出業者)の人も、楽しそうに生きていたんです。エクスポーターの事務所の人たちも、毎日会っているのに、毎日ハグを交わしている。目が爛々と輝いている生産者の人たちからは、まだまだおいしいものを作れるんだという情熱やプライドを感じました。
そんなふうに僕たちの知らない豊かさを見せつけられたときに気づいたのは、彼らのためにコーヒーで何かをしてあげたいと思うこと自体、おこがましいということ。彼らと対等な関係を築き、同じ目線に立たないと、コーヒーに関わっている意味がないと感じたんです」

コロナ禍の2020年7月に「aoma coffee」をオープンしてから半年強。「コーヒーの消費量を増やし、特定の生産者からまとまった量を定期的に購入できる店にすること」が今の目標だという。
「定期購入する生産者を1年に1人のペースで増やしていきたいと思っています。焙煎をするようになってから8年ほど経つと、この人の豆を買いたいと思う生産者が出てくるのですが、いつかその生産者のもとを訪れて『実は4年くらいずっと、あなたの豆を買ってるんだよ』と言いたいんです。そのためにも人を雇用して、aoma coffeeというブランドを盛り上げるチームをつくり、きちんとお金が循環するビジネスにしていきたいと思っています」

「コーヒーのおかげで人ありきの自分になった。コーヒーが、閉ざしていた僕の人生を開いてくれた」と青野は言う。
「染物職人だった20代の頃は、アーティスティックな生き方に憧れていたんです。コーヒーで言うなら、おれがこんな味にしてやったんだぞ、というような考え方をしていた当時の自分を思い返すと恥ずかしくなる。でも、そんな時代があったから今があるのだとも思います」

「美味しいコーヒーで飲む人の情緒を動かし、それをコーヒーの未来に繋げること」を使命とする今の青野に、昔のような面影はない。
「あくまでも生産者がつくったおいしいコーヒーありきです。バランスをうまく取りながらその豆の個性を活かした結果、お客さんが『おいしい』と言ってくれたらそれでいい。その理由が僕のテクニックであれ、素材であれ、どっちでもいいんです」
対等な関係から生み出される調和した世界に、aoma coffeeの個性は宿っているのかもしれない。
Interview,Text:中道 達也
MY FAVORITE COFFEE人生を豊かにする「私の一杯」
休日の朝などに、妻と飲むコーヒーを淹れていると、ハンドドリップに興味を示す2歳半の息子が近寄ってきます。主に友人のロースターからもらった豆を家庭用のミルで挽き、HARIOのV60で淹れています。あまり難しく考えず、ラフに淹れるようにしているのは、お客さんの感覚を忘れないためでもあります。

このロースターのコーヒー豆を購入する








